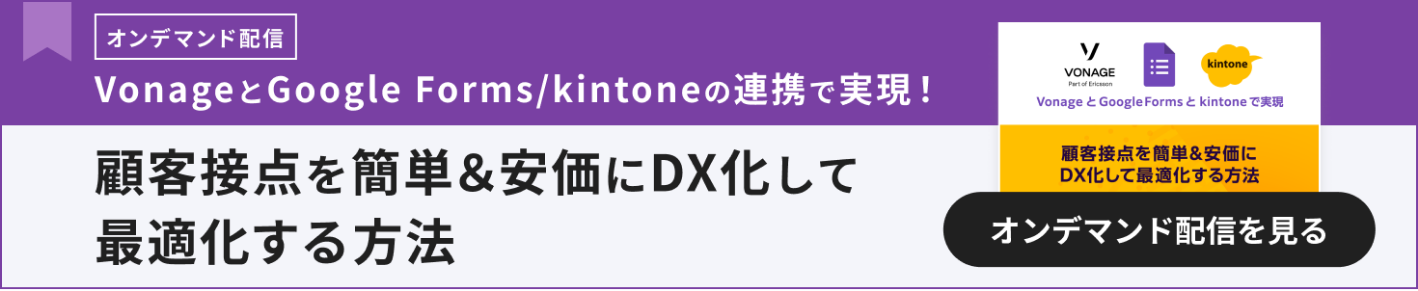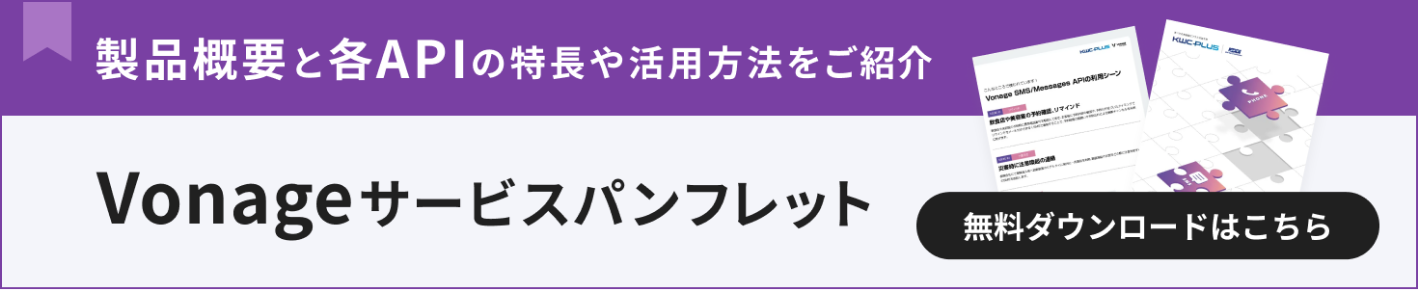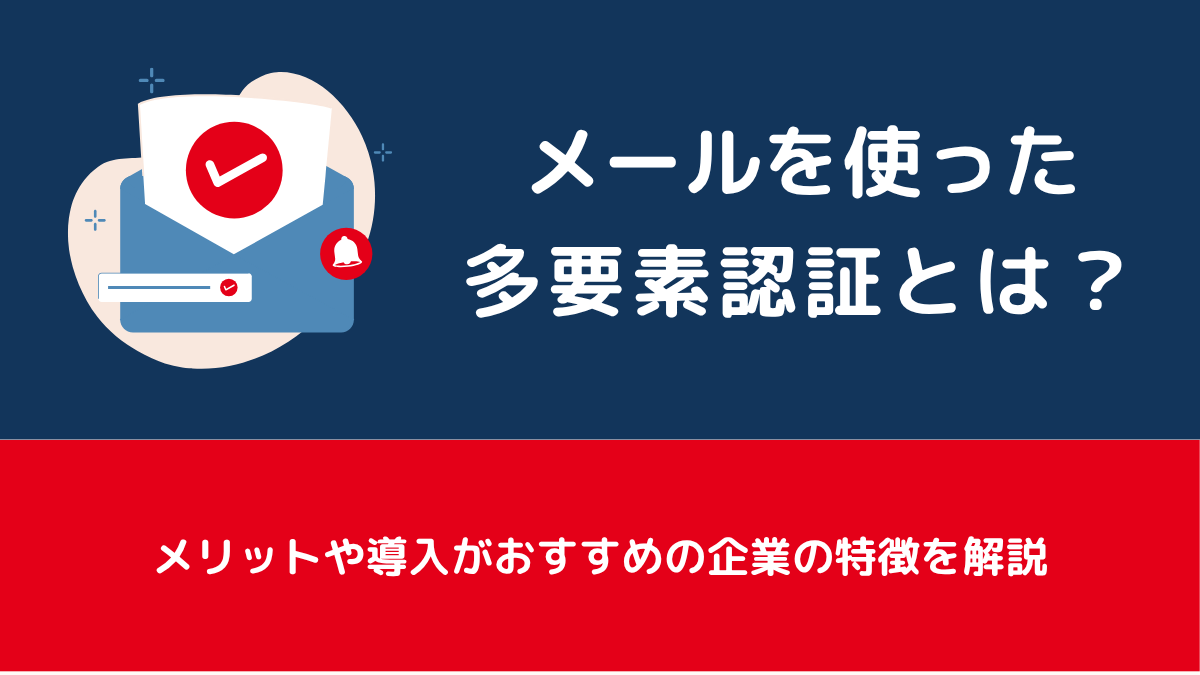SSO(シングルサインオン)とは?導入するメリットや認証方法の種類をわかりやすく解説
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ

テレワークやクラウドサービスが普及し、業務で利用するシステムやサービスの数が増えたことで、ログイン認証の複雑さや管理業務の負担に悩まされている企業も多いでしょう。
そこで注目されているのが、SSO(シングルサインオン)です。本記事では、SSOの仕組みや導入メリット、認証方式の種類、システムの選び方などを詳しく解説します。
SSOとは

シングルサインオン(SSO:Single Sign On)は、複数のシステムを一度のユーザー認証で利用できるようになる仕組みです。一度どこかで認証を行えば、以降、その認証に紐づけられている複数のシステムやアプリケーション、サービスを追加認証なしで利用できるようになります。
従来は各システムごとに個別のID・パスワードでログインする必要がありました。しかしSSOでは、一度ログインすれば追加認証の必要がありません。そのため、複数のクラウドサービスを利用する際などに便利です。
SSOが注目を集める背景
近年ではテレワークの普及やSaaSの活用の増加により、業務で利用するシステムの数が増えたことで、各サービスのID・パスワードを個別に管理することが困難になっています。これは、IT管理者や、ユーザーとなる従業員の双方にとって大きな負担となります。
またフィッシング詐欺やパスワードリスト型攻撃など、認証情報を狙ったサイバー攻撃のリスクも年々深刻化しています。そのため、パスワードの漏洩リスクを軽減する対策が求められるようになってきました。
このような背景から、元々は社内ネットワークやオンプレミス環境向けに導入されていたSSOが注目を集めるようになったのです。一度の認証で複数サービスへ安全にアクセスできるSSOは、その利便性から急速にニーズが急速に高まっています。
SSOを導入するメリット

SSOを導入する主なメリットについて、それぞれ見ていきましょう。
ログインにかかる従業員の手間を削減できる
SSOを導入することで、従業員は一度のログイン操作で業務に必要な複数のシステムやクラウドサービスへアクセスできるようになります。これまで個別にログインしていた作業がわずか1回の認証で一括完了できるため、毎日のログイン時間が短縮され、業務がスムーズに開始できるでしょう。
またSSOでは、複数のIDやパスワードを覚える必要がありません、パスワードを忘れたことによるリセット依頼の手間も軽減されます。
IT部門の管理コスト・負担を軽減できる
SSOでは、すべてのアカウント情報を一元管理できるため、IT部門や情報システム部門の業務負担が大幅に軽減されます。新入社員へのアカウント発行や退職者の権限削除など、これまで個別対応が必要だった作業を簡素化できるのです。
したがって、対応の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクも回避できます。また従業員からのパスワード再発行依頼が減少することで、ヘルプデスクの対応件数も削減されるでしょう。その結果、限られたリソースをセキュリティ対策の強化やDX推進といった、コア業務に充てることが可能です。
組織全体のセキュリティレベル強化が可能となる
従来の環境でセキュリティを確保するためには、各システムに対して、異なるID・パスワードの設定が必要でした。しかし管理が煩雑になることから、従業員が同じパスワードを使い回したり、簡易なパスワードを設定したりといったリスクを抱えていたのが実情です。
SSOを導入し、単一の強力なパスワードに統一することで、ログイン作業が効率化されると同時に、セキュリティ強化も実現します。
さらに、SSOは多要素認証(MFA)との併用も可能です。推測が困難なパスワードに加えて、生体認証やワンタイムパスワードなどの追加認証要素を組み合わせることで、認証のセキュリティレベルが高まります。またセキュリティポリシーの一元適用やアクセスログの集中管理、退職者アカウントの即時無効化といった機能で、組織全体のセキュリティガバナンスの向上が期待できます。
関連記事はこちら
SSOの認証方式
SSOには複数の認証方式が存在し、それぞれに特徴があります。代表的な認証方式について詳しく解説します。
リバースプロキシ方式

リバースプロキシ方式は、ユーザーがアクセスするWebシステムと実際のアプリケーションサーバーの間に「リバースプロキシ(中継サーバー)」を設置し、認証を代行させる方法です。ユーザーがWebアプリケーションにアクセスした際、リバースプロキシが認証サーバーと連携して、ID・パスワードを用いて自動的にログインを行います。
この方式は、プラットフォームを問わず導入しやすいです。各システムにエージェントソフトウェアをインストールする必要がないため、管理負担が少ないという特徴があります。ただしネットワーク構成の変更が必要だったり、アクセス集中による通信遅延が発生する可能性がある点には注意しましょう。
エージェント方式

エージェント方式は、各Webサーバーやアプリケーションサーバーに「エージェント」と呼ばれる専用ソフトウェアをインストールし、ユーザーの認証を代行する仕組みです。ユーザーがシステムへアクセスすると、エージェントがバックエンドのSSO認証サーバーに認証状況を確認し、問題がなければ自動的にアクセスを許可します。
この方式の特徴は、ネットワーク構成の変更が不要な点です。そのためアクセス集中時でも安定した稼働が見込めます。一方でサーバーごとにエージェントの管理やバージョン更新が必要となり、対応OSに制限がある場合もあるため、導入前に確認しましょう。
既存のネットワーク構成を変更せずにSSOを導入したい企業に適しています。
代理認証(フォームベース)方式

代理認証方式は、ユーザーの端末(パソコンやスマートフォン)に常駐する「エージェント」が、各システムへのログイン作業を代行する仕組みです。ユーザーがWebシステムにアクセスすると、端末上のエージェントがログイン画面を検知し、あらかじめ登録されたID・パスワードを自動入力してログインを完了させます。
他の方式と比べて導入が容易で、既存システムを改修せずに済むのがメリットです。一方で、端末ごとにエージェントのインストールが必要となるほか、大規模環境での拡張性には課題があります。レガシー環境とクラウドサービスが混在する中小企業などに適した方式です。
SAML方式(フェデレーション方式)

SAML方式(フェデレーション方式)は、異なるシステム間での認証連携を実現するための標準プロトコルです。ユーザーが一度クラウドサービスにログインすると、IDプロバイダー(IdP)が「アサーション」と呼ばれる認証情報を発行し、他のクラウドサービス(SP:サービスプロバイダー)への認証を自動で連携します。特にクラウドサービスに特化したSSO方式です。
Google WorkspaceやSalesforce、Microsoft 365など、主要なクラウドサービスとの互換性が高く、セキュリティ性・安定性の両面で優れています。一方で、既存のオンプレミスシステムでは利用できない場合があり、国内サービスへの対応状況も事前に確認が必要です。クラウドSaaSを多用する企業に適しています。
※Google Workspaceは、Google LLC の商標です。
※Salesforceは、Salesforce, Inc. の商標です。
※Microsoft 365は、Microsoft Corporationの商標です。
透過型方式

透過型方式は、ユーザーがアクセスするWebアプリケーションを監視し、認証が必要なタイミングで自動的にログインを代行するSSO方式です。通常は「透過型サーバー」と呼ばれる中継サーバーを経由し、ユーザーの認証情報を裏側で送信するため、ユーザー自身はログイン操作を意識する必要がありません。
ネットワーク構成を変更せずに導入でき、クラウドとオンプレミスの混在環境にも対応可能です。また、多様な端末やブラウザで利用できるのも特長です。ただし、透過型認証に対応したSSO製品が前提となるため、選定時には対応状況を確認しましょう。
SSOを導入する際の注意点

SSOは多くのメリットをもたらす一方で、注意すべき点もあります。どのようなものがあるか、詳しく見ていきましょう。
システムトラブル発生時の影響が広範囲に及ぶ可能性がある
SSOは、ユーザー認証を一元的に管理するための認証基盤が中心的な役割です。しかしこの認証基盤がトラブルを起こした場合、依存するすべてのアプリケーションやサービスにログインできなくなる恐れがあります。
たとえば認証サーバーがダウンすると、メール、勤怠管理、業務システムなどへのアクセスがすべて停止し、組織全体の業務が一斉に止まってしまうリスクがあります。そのため、大規模な組織や医療・金融など業務を停止できない業種においては、冗長構成の導入やバックアップ認証手段の準備など、システム対策が欠かせません。
不正アクセス時に被害が甚大化するリスクがある
SSOは、単一の強力なパスワードを用いて複数のシステムにアクセスできるという、高いセキュリティ性能と利便性の両立が可能です。しかしその1つのパスワードが流出してしまった場合、社内のさまざまなシステムやクラウドサービスに不正にアクセスされ、被害が甚大化する恐れがあります。
またSSOシステムそのものが攻撃対象となった場合、侵入者が社内全体の機密情報や顧客データへ自由にアクセスできる状況になりかねません。重大な情報漏洩や業務妨害のリスクを軽減するためには、パスワード強化に加えて、多要素認証の導入、アクセス権限の適切な設定、ログ監視の強化など、万が一に備えたセキュリティ対策が重要です。
初期導入にコストがかかる
SSOを導入する際は、初期設定やシステム構築に一定のコストと専門的な知識が求められます。特に既存の社内システムとSSOを連携させる場合、プラットフォームごとの仕様差に対応するため、技術的ハードルや工数が発生しやすいです。また一部のクラウドサービスではSSO機能が有料オプションになるケースもあり、ライセンス費用が当初の想定を上回ることもあるでしょう。
ただし、導入後の運用負荷軽減やセキュリティ強化による将来的なコスト削減効果を踏まえれば、長期的には費用対効果の高い投資と捉えられます。初期投資を回収するまでの期間や、運用コストの削減効果を試算したうえで、導入判断を行うことが重要です。
SSOを選ぶ際のポイント

SSO製品・サービスは多種多様のため、自社のニーズにマッチした製品を選ぶには、複数の観点から評価する必要があります。主なポイントについて、詳しく見ていきましょう。
提供形態
SSOを提供する方式には、主にオンプレミス型とクラウド型の2種類があります。
オンプレミス型は自社サーバーに認証基盤を構築するため、細かい設定や高度なカスタマイズが可能です。社内に専門人材がいる企業や、自社独自の認証環境を構築したい企業に適しています。
一方、クラウド型はサービスプロバイダーが管理・運用する方法で、短期間で導入でき、インフラ管理の手間も少ないのが特徴です。管理・運用のリソースを抑えながらスピーディに認証環境を整えたい企業には、クラウド型が適しているでしょう。
これらを踏まえ、自社の環境や導入目的に応じて適切な提供形態を検討しましょう。
既存システム・利用したいシステムとの互換性
SSOを導入する際は、連携予定のシステム・サービスが対応している認証プロトコル(SAML、OAuth、OpenID Connectなど)と互換性があるかどうかを事前に確認しましょう。
多くのSSO製品は、Google WorkspaceやMicrosoft 365など、代表的なクラウドサービスとの連携に対応しています。ただし製造業向け生産管理システムや電子カルテなど、業種特化型のシステムでは対応状況が分かれることもあります。
またAPI連携の柔軟性や、既存のオンプレミス環境とのなじみやすさも重要です。
セキュリティ性
SSOは利便性が高い一方、システム自体が攻撃を受けた場合に、影響範囲が広がりやすいです。万が一、不正侵入を許すと、すべての連携先システムにアクセスされるリスクがあるため、SSOサービス自体のセキュリティレベルが高いものを選びましょう。
加えて、生体認証、電話認証、IPアドレス制限、クライアント証明書の活用など、セキュリティレイヤーを多重に組めるかどうかも大切です。利便性とセキュリティを両立するためにも、セキュリティの基盤が整っているか、また将来的な脅威に対応できる拡張性があるかを確認しておきましょう。
利便性・使いやすさ
SSOは、ユーザーとなる従業員と管理者の両者にとって使いやすいシステムが望ましいです。ITツールに不慣れな従業員でも直感的に操作できるUIかどうか、管理者側の画面設計が分かりやすくシンプルかといった観点で確認しましょう。多機能であっても、導入時の設定や日々の運用が煩雑だと、担当者の負担増・運用コスト増につながるため注意が必要です。
自社の情報システム担当がスムーズに管理できるか、導入後のリソース配分は適切かを見極めるためにも、事前のデモンストレーションや試用期間を活用して使用感を確認しましょう。
サポート体制・導入実績
ベンダーのサポート体制が充実しているか、導入支援サービスや運用開始後のトラブル対応、カスタマーサポートを備えているかも重要です。導入支援の有無、運用中のトラブルへの対応スピード、チャットや電話などのサポート手段、サポート時間帯などをあらかじめ確認しておきましょう。
また、自社と同業種・同規模の企業での導入実績があるか、自社が利用中のクラウドサービスとの連携実績があるかも重要なポイントです。多くの企業で導入されている実績があるベンダーなら、運用ノウハウも豊富で、導入後も安心して利用を継続できるでしょう。
まとめ
SSO(シングルサインオン)は、一度ユーザー認証を行うだけで複数のシステムにアクセスできる仕組みのことです。近年、ID・パスワードの個別管理が煩雑になり、パスワードを狙ったサイバー攻撃のリスクも高まっていることから、SSOが注目されています。SSOの導入では、ログイン作業が効率化され、組織全体のセキュリティレベルが高まることなどがメリットです。
ただし導入にあたっては、自社の環境に適した認証方式の選択や、システムトラブル時の対策、セキュリティリスクへの備えなど、慎重な検討と準備が欠かせません。提供形態、互換性、セキュリティ性、利便性、サポート体制といった観点から総合的に評価し、最適なSSO製品を選定しましょう。
「Vonage」は、メールや電話、SMSなど、さまざまなコミュニケーションチャネルを連携・統合できるクラウドサービスです。SSOとクロスドメインID管理システムを搭載しており、会社の資格情報を元に、簡単にビジネスアプリケーションにログインできます。Vonageの詳細や機能、導入事例などは以下のサイトを参考にしてください。
執筆・監修者
- カテゴリ:
- 多要素認証