更新日:
公開日:
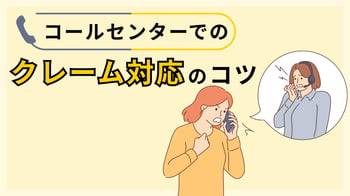










更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ
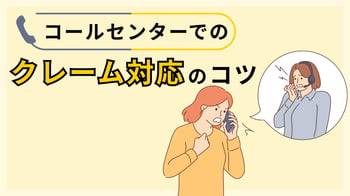
コールセンターにおいて、クレーム対応は避けて通れない業務のひとつです。しかし、どのように対応すればよいのかわからず、負担に感じる方も多いのではないでしょうか。クレームへの適切な対処法を身につければ、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現できます。
この記事では、クレームが発生する原因や、対応のコツ、対応する際のポイントなどを解説します。
クレーム対応を効果的に行うためには、まずクレームが発生する根本的な原因を理解することが欠かせません。クレームが発生する主な原因は、以下のとおりです。

ここでは、上記の原因について詳しく見ていきましょう。
クレームの主要な原因として、企業が提供する商品やサービス、または企業そのものに対する不満が挙げられます。具体的には、購入した商品がすぐに壊れるといった不具合、機能の欠陥、操作の複雑さ、顧客の期待に応えられなかったことなどです。
問い合わせを行った際のオペレーターの対応が悪かったことで、顧客の不満や怒りが増幅し、クレームに発展することがあります。たとえば次のようなケースが該当します。
これらが原因となっている場合は、マニュアルの更新や、人材教育の時間を確保するためにツールの導入により業務効率化を図るといった対策が必要です。
関連記事はこちら
商品やサービスに大きな過失が認められないにもかかわらず、不当な要求をしたり、嫌がらせをしたりする、クレーマーによるクレームも存在します。
具体的には、過度な慰謝料を要求、実際の問題がないにもかかわらずオペレーターの対応が悪いと主張する、遠隔地への自宅訪問や土下座を強要するなどという理不尽な要求が含まれます。
効果的なクレーム対応には、段階的なアプローチが不可欠です。以下のような手順で対応しましょう。

ここでは、ステップごとに解説していきます。
電話がつながるまでに、顧客の不満が高まっているケースも少なくありません。保留や転送などで待たせる時間はできるだけ短くし、迅速かつ丁寧に応答することが大切です。
もし待たせてしまった場合は、「大変お待たせいたしました」「お待たせしてしまい大変申し訳ございません」といった謝罪の一言を添えます。
顧客からクレームが伝えられたら、まずは不快な思いをさせたことに対して、誠心誠意謝罪することが重要です。
「申し訳ございません」だけでなく、「この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」「不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」など、具体的に何に対する謝罪かを伝えます。声のトーンや表情にも気を配り、誠意がしっかり伝わるように意識しましょう。
顧客の態度や会話内容から、顧客が何を求めているのか、何が不満の原因なのかを、落ち着いて把握する必要があります。このとき焦って早口になったり、顧客の話を途中で遮ったりせず、相手の言葉を最後まで丁寧に聞く姿勢を持ちましょう。
不明点は「恐れ入りますが」「誠に申し訳ございませんが」などのクッション言葉や相槌などを置きながら、「〇〇の件でご不便をおかけしているということでよろしいでしょうか?」などの言い回しを用いて、双方の認識をすり合わせます。
メモを取りながら話を整理し、後の対応に備えることも欠かせません。文字起こしツールなどを活用すれば、負担を減らしつつ対応の質を高められるでしょう。
顧客のクレーム内容を把握したら、相手の感情にしっかり寄り添い、受け止める姿勢が大切です。「○○だったのですね」「それはご不便でしたね」など、相手の言葉を繰り返しながら相槌を打つことで、「自分の気持ちを受け止めてくれた」という安心感が生まれ、顧客の気持ちも落ち着きます。
ただし、不自然に相槌を打ちすぎるとかえって不快感を与えかねないため、自然なやり取りを心がけてください。
すべての話を聞いた上で、返金・交換・再送など具体的な解決策を提示します。専門用語を避け、誰にでも理解できる言葉で説明しましょう。
また、「このような対応を考えておりますが、いかがでしょうか?」など、提案が一方的にならないよう丁寧な言い回しを意識することで、押し付け感を和らげ、納得感を高められます。問題解決への前向きな姿勢と具体案をセットで提示するのが効果的です。
最後に、意見を寄せてくれたことに対して改めてお詫びと感謝を伝えます。「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした」「ご迷惑をおかけしたにもかかわらず、丁寧にお話しいただき感謝いたします」と誠心誠意伝え、企業の信頼回復に努めます。
終話時のトーンを穏やかに保つことで、相手に安心感を残せ、企業の印象にも好影響を与えられるでしょう。
クレーム対応はその場限りで終わらせず、再発を防ぐための記録と共有が欠かせません。通話の録音や詳細なメモを残すことで、トラブル時の証拠になるだけでなく、対応の振り返りや情報共有にも活用できます。
対応履歴や改善事例をデータベース化し、マニュアルやFAQの更新、教育研修に役立てれば、コールセンター全体の対応力の底上げにも寄与するでしょう。
効果的なクレーム対応の実現には、技術的なスキルだけでなく、オペレーターのメンタルへの配慮も不可欠です。対応時に大切にするポイントとして、以下の3点をご紹介します。

ここでは、上記のポイントを解説していきます。
顧客の怒りの対象はあくまでも商品やサービスであり、オペレーター個人ではないと意識しましょう。そうすれば、過度に感情を引きずられず、冷静に対応しやすくなります。
また、電話対応を振り返る際は、改善点だけでなく、よかった点を見つけることも大切です。ある程度割り切って、次に活かすために前向きな気持ちを保つことが、長期的な業務継続の鍵となります。
クレーム対応は、言葉の選び方ひとつで状況が悪化することもあります。無自覚に配慮のない言葉を使ってしまうと、顧客の怒りをさらに強めてしまうおそれがあるため、注意しなければなりません。
事前に以下のようなNGワードを知っておくことで、感情のこじれを防ぎ、よりスムーズな解決が可能となります。
| NGワード | 理由・注意点 | 代替表現例 |
| 「お言葉ですが」 「そのようなことはございません」 |
顧客の主張を否定する印象を与え、感情を逆撫でしてしまう | 「そのように感じられたのですね」 「お気持ちはよく分かります」 |
| 「私の担当ではありません」 「部署が違いますので」 |
責任逃れ・たらい回しの印象を与える | 「私の方で確認いたします」 「責任を持って対応いたします」 |
| 「でも」 「だって」 |
言い訳・反論と受け取られ、謝罪の誠意が伝わらない | 「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません」 |
| 「たぶん」 「おそらく」 「思います」 |
曖昧な印象を与え、誠実さや信頼性が損なわれる | 「確認のうえ、折り返しご連絡いたします」 |
| 「ちょっと待ってください」 「そう決まっておりますので」 |
命令口調や押しつけがましさを感じさせる | 「恐れ入りますが〜していただけますか?」 |
| 「お気持ちはわかりますが※その後に否定が続く)」 | 共感のように見えて、実際は話を遮断してしまう | 「ご不快なお気持ち、よくわかります」+対応案 |
クレームの内容が複雑な場合や、オペレーターの判断や権限を超える場合は、無理に対応を続けず、速やかに上司や専門部署へ引き継ぐべきです。即時解決が難しい場合は、「◯分以内に折り返します」と明確に伝えることで、顧客の不安を軽減できます。
なお、現場が迷わず判断するために、上司や専門部署へ引き継ぐ場合の基準や手順を明確にしておきましょう。組織として迅速かつ誠実に対応する姿勢が、顧客からの信頼を得ることにつながります。
クレーム対応の質を向上させることも重要ですが、クレームの発生自体を減らす対策にも着目すべきです。具体的には、以下のような対策が挙げられます。

ひとつずつ見ていきましょう。
クレーム対応の振り返りは、サービス品質の向上やトラブルの未然防止につながる重要な機会となりえます。そのため、対応ごとに「何が原因だったのか」「対応は適切だったか」などを確認し、VOC(顧客の声)として記録・分析することが肝心です。これにより、改善点や潜在的な課題を見つけられます。
こうした情報は、トークスクリプトや教育に活かせるのはもちろん、商品・サービスの見直しや新たなアイデアのヒントにもなるでしょう。コールセンターだけの問題として捉えるのではなく、全社で共有・活用することで、顧客・従業員満足度を高めることが可能となります。
対応の品質を維持・向上させるためには、通話録音の活用が有効です。録音データは、万一トラブルが起きた際の証拠として機能するのに加え、優れた対応例や注意すべきやり取りを共有する教育資源にもなります。
録音を聞き返せば、自分の話し方の癖や改善ポイントにも気づきやすくなり、オペレーター自身のスキル向上にもつながるでしょう。また、通話の冒頭で「本通話は品質向上のため録音させていただいております」と通知することで、顧客の過度な要求や言動を抑止する効果も期待できます。
関連記事はこちら
オペレーターの応対力を高める手段として、AIによるリアルタイム支援も効果的です。たとえば、通話中の話速・沈黙・被りなどを数値化して表示し、話しすぎやタイミングのズレに即座に気づける仕組みを導入すれば、やり取りの質が向上します。
また、感情分析機能を使えば、顧客の怒りや不満が高まったタイミングを可視化し、SVが素早く介入できる体制も構築可能です。対応の質を定量的に把握することで、根拠のある改善が可能になるほか、スキルの底上げに寄与するでしょう。
コールセンターでのクレーム対応は、適切な手順とポイントを押さえることで、顧客満足度の向上と業務効率化を同時に実現できます。そのためには、クレーム発生の原因を理解し、段階的なアプローチで対応することが重要です。
また、NGワードの回避や感情移入のコントロール、自分で判断できない場合は上司へ引き継ぐなど、細かな配慮も欠かせません。さらに、クレーム対応の質を向上させるだけでなく、そもそものクレーム発生を減らすための対策にも取り組むべきです。原因分析、通話録音の活用、AI技術の導入などを通じて、継続的な改善を図ることが求められます。
「MiiTel」は、通話の自動録音・文字起こし、トーク分析、感情分析が可能なソリューションです。クレームの記録・振り返りを効率化し、対応品質の底上げに貢献します。
また、クレーム発生後の対応だけでなく、未然に防ぐための仕組みづくりにも活かせます。コールセンター全体のクレーム対応力を強化し、顧客満足度の向上を目指したい方は、ぜひご活用ください。