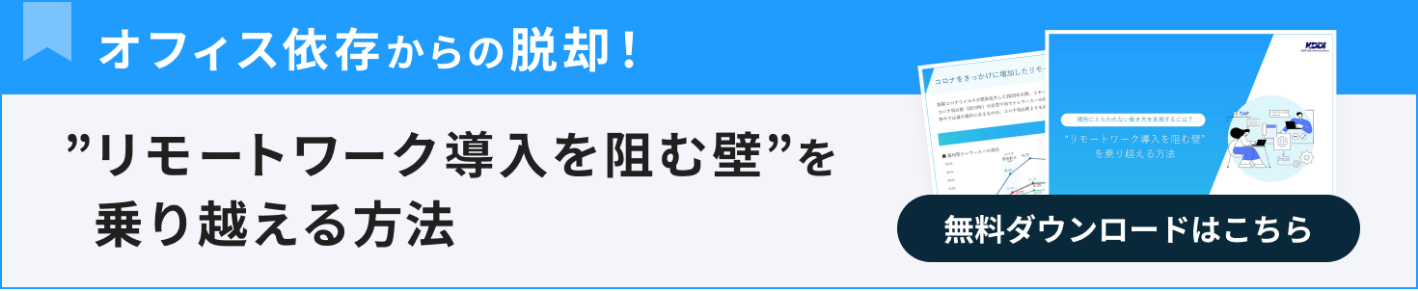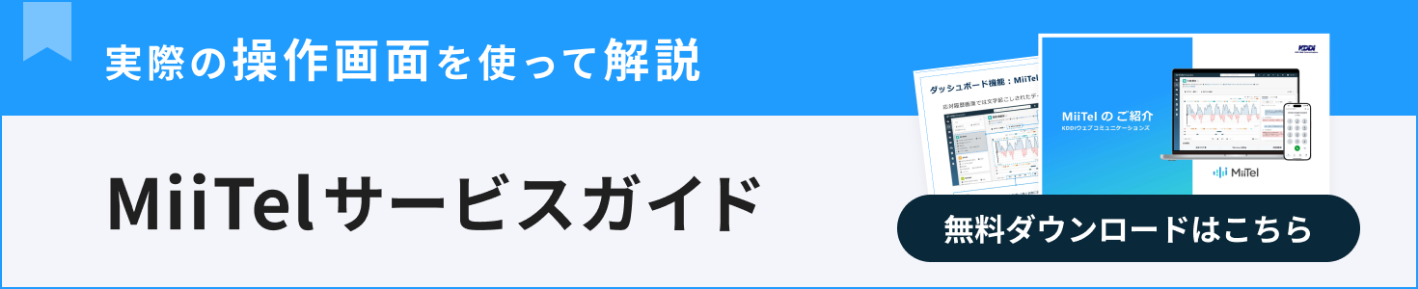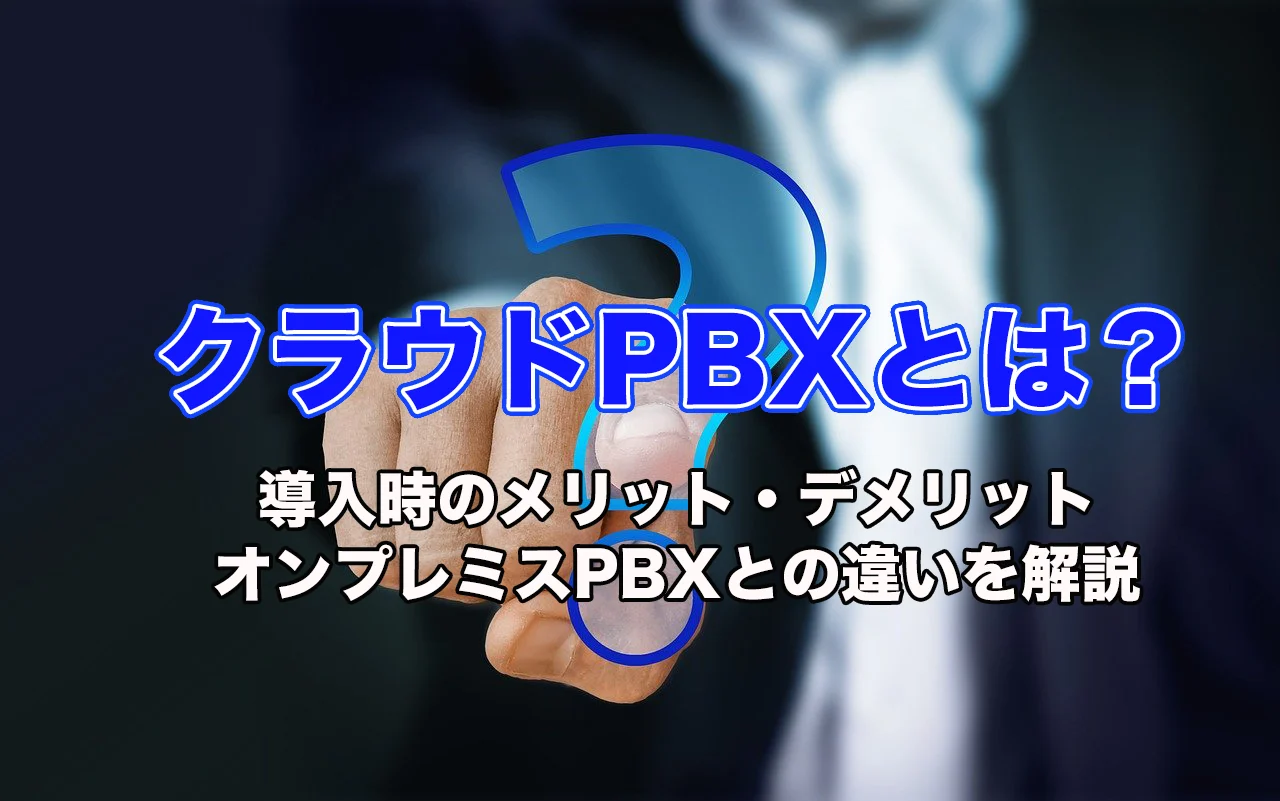【図解あり】PBXとは? 種類や活用方法、ビジネスフォンとの違いなどを詳しく解説!
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ

オフィスやコールセンターなど、いまや多くのビジネスシーンに欠かせない存在となっている「PBX」。対顧客だけでなく、社内でコミュニケーションをとるうえでも重要な役割を果たしています。
しかしPBXについて詳しく知っている、具体的に説明できる……という方は少ないのではないでしょうか。
そこで本記事では、まずPBXの基本的な機能や仕組みをご紹介します。そのうえで種類ごとの活用方法やビジネスフォンとの違い、さらには導入時のポイントなどについても解説していきます。
PBXとは?

PBXは「構内交換機(Private Branch Exchanger)」のことを指す略語で、別名「電話交換機」とも呼ばれています。
主に事業規模の大きな企業・団体・コールセンターなどで導入されている、音声通話によって社内外のコミュニケーションを円滑化するための装置です。
企業のオフィスで、デスク上に複数の電話機が設置されている場面を見たことはありませんか? それらの電話機で使える機能を制御しているのが、このPBXなのです。
PBXが導入された背景
PBXが必要とされるようになったのは、通信費用がかかる限られた電話回線に対して、多くの電話機を接続したいというニーズが生まれたためです。
電話回線に複数の電話機を接続するには、まず施設内(オフィス・店舗など)にPBXを設置し、そのPBXと電話機を接続する必要があります。そしてそれぞれの電話機同士を接続することで、PBXが施設内の電話回線を集約。外線(公衆回線)への発着信や内線通話、転送を可能にします。
PBXの最新事情
電話がコミュニケーションの主役だった時代は、社内の内線通話を無料にできることがPBXを活用するメリットでした。
特にタンデム接続(PBXを拠点ごとへ分散させて専用機でつなぐ)によって、拠点間の通話が無料になるだけでなく、相手先にもっとも近い拠点から外線発信することでコストを抑えられる面もあったのです。
しかし一方で、複数台のPBXを管理することによって、初期費用がかさんでしまうデメリットがありました。そのため最近では、IP-PBXのような「1台に集約できるPBX」や、そもそも「専用機器を必要としない」クラウドPBXを用いて、コスト削減を図る企業も増えてきています。
ビジネスフォンとの違い

ビジネスフォンは、専用の主装置をオフィス内へ設置することで複数のビジネスフォン専用機を取りまとめ、外線の発着信や内線を共有できる電話機のことを言います。外線との発着信や内線での通話転送が可能なほか、1つの電話回線を複数の内線で共有できるなどPBXと共通する機能があるためしばしば混同されがちです。
ここではPBXとビジネスフォンの違いをそれぞれ解説していきます。
接続できる容量の違い
ビジネスフォンの接続可能台数
ビジネスフォンの場合、接続できる電話機の目安は数台~数百台ほど。小規模~中規模の事業者向けです。
PBXの接続可能台数
一方PBXは中規模~大規模の事業者向けが主流で、数十台から数千台以上までと幅広い数の接続に対応できます。
システムの耐久性・安定性の違い
ビジネスフォンのシステム耐久性
ビジネスフォンは主装置にCPU(Central Processing Unit)という中央処理装置のデバイスを使用しており、システムがダウンすると使用できなくなります。
緊急時用のバッテリーを使用しても稼働を延長できる時間は3時間ほどのため、停電装置の設置など別の対応方法との併用が必要です。
PBXのシステム耐久性
一方PBXの場合は、高性能CPUを二重化して実装しています。万が一ひとつ目のCPUが故障しても、もう一方で処理を継続できるため、耐久性・安定性ともに勝っていると言えるでしょう。
停電などの際は停電用バッテリーを使用することで、一日程度であれば動作を継続できます
導入コストの違い
ビジネスフォンの導入コスト
ビジネスフォンの導入コストは、新規導入を想定した場合、以下のものに対して発生すると考えられます。
- 電話機購入(新品購入のほか中古品購入、リース契約など)
- 電話加入権の取得費用や契約料
- ビジネスフォン主装置の購入・設置費用
- 主装置と電話機をつなぐ工事・配線工事など、設置に伴う各種工事費用
- ビジネスフォンと同時に複合機を設置する場合は、その購入・設置費用
電話機代・工事費用をあわせると数十万円~数百万円(電話機の台数にもよる)が目安です。
PBXの導入コスト
PBXの導入コストは、PBXの種類により異なります。
オンプレミスPBXの場合
オンプレミスPBXの場合、以下のような導入コストが想定されます。
- 回線の設定費用(アナログ回線、ISDN回線、IP回線など)
- PBX主装置の購入と設置費用
- 電話機・配線コードなど必要備品の購入・設置費用
- 主装置と電話機をつなぐ工事・配線工事など設置に伴う各種工事費用
オンプレミスPBXの導入に必要な初期費用は数百万円~数千万円と高額になりがちです。ただし基本的に月額利用料は不要なため、自社に合うサーバーを導入し、長期的に利用することで運用コストを抑えられます。
クラウドPBXの場合
クラウドPBXの場合、初期費用はオンプレミスPBXに比べると安く済みます。これは物理的なPBX主装置をオフィス内へ設置するなどの購入・工事費用が不要で、接続する端末も電話機に限らず幅広く利用できるためです。
運用コストの違い
ビジネスフォンの運用コスト
運用コストに関しては、一度設置が完了すると買い替えや移転などがなければ大きな費用がかかることはありません。維持費としては以下のようなものが挙げられます。
- 毎月の電話料金
- 電話回線の月額基本料金
- 毎月のリース料金(リース契約をしている場合のみ)
- 保守契約料金(メンテナンス契約を結んでいる場合)
- 転送機能の月額料と利用料金(契約を結んでいる場合)
そのほか考えられる追加費用は、以下があげられます。
- 電話機を買い足す場合(本体料金、設置工事費用、主装置との接続費用)
- 追加の電話番号を取得する場合(新規電話番号取得費用、主装置との接続費用)
PBXの運用コスト
PBXの運用コストは、PBXの種類により異なります。
オンプレミスPBXの場合
運用コストには以下のものが想定されます。
- 毎月のリース料金(リース契約をしている場合のみ)
- 毎月の通信費
- 人件費(保守管理)
- 定期的なメンテナンス費(ソフトウェアアップデート、障害発生時の対応)
追加の費用として考えられるのは、オフィスの拡張や移転の場合です。本体を移動させる作業と電話環境の再設定が必要なため、再設置に関わる各種工事費用が必要になります。
また拠点数を増やす場合は、別途新たにPBX主装置と接続する端末の費用や各種工事費用がかかります。
クラウドPBXの場合
クラウドPBXの運用コストとしては、以下などが考えられます。
- PBXの月額料金(費用はユーザーごとに発生し、各ベンダーの料金プランにより異なります)
- インターネット月額使用料(拠点ごとに発生)
- プロバイダ料金(拠点ごとに発生)
- 外線通話料金(拠点ごとに発生)
従来必要だった保守や定期的なメンテナンスに関してはクラウドPBXのベンダー側が行うので、運用費や運用に割いていた時間が削減されます。
利用する人数や拠点数などによって導入に向いている PBX の種類はそれぞれ異なります。 PBXの場合は料金だけではなく、特徴もあわせて比較するとよいでしょう。
PBXの種類
PBX は大きく分けると「従来型(レガシー)PBX」「IP-PBX」「クラウドPBX」の3種類があります。ここではそれぞれの特徴と、導入時に想定されるメリット・デメリットについて簡単にまとめます。
従来型(レガシー)PBX

レガシー(従来型)PBXは、 PBXの種類の中で一番長い歴史を持つタイプです。1890年に日本へ導入されて以来、改良が進められてきました。
レガシーPBXは電話回線を利用して電話同士をつなぎます。またオフィス内へ物理的な装置(主装置)を設置して利用します。
PBX主装置はおおまかに筐体(きょうたい)とパッケージの2つに分けられます。
筐体は主装置の外観にあたるもので、パッケージを収納する箱のことです。接続可能数は機種によって異なり、接続規模にあわせて筐体を増やすことで容量も増やせます。一方でパッケージはPBX内に実装する基盤のことで、機能ごとに用意されているものです。設置先に応じてパッケージの組み合わせは異なります。
外線や内線など、各機能のパッケージごとの回路にデータ設定を行うことで、主装置によって専用の番号が割り当てられます。これにより、電話機同士がPBXを通じてつながるようになるというわけです。
なお回線切り替えを制御する「CPU( Central Processing Unit)」と呼ばれる中央処理装置は、どのPBXにも必ず実装されています。
IP-PBX

IP-PBXは、専用機器を設置してIP電話機とIPネットワークを接続することで、レガシーPBXと同じ機能を利用できるタイプです。仕組みに関しては、基本的にレガシーPBXと大きく変わりません。使用するのが電話回線かIPネットワークかの違いがあるのみです。
IP-PBXの特徴としては、通話がIPネットワーク内で完結することで、安定した通話を実現できる点が挙げられます。VoIP(Voice over Internet Protocol)と呼ばれる、ネットワーク上で音声を送受信する技術を使用して、インターネットを介する音声をやり取りすることも可能です。なおインターネット経由で通話する場合はベストエフォートの回線を利用するため、通話品質が担保されません。この点については注意しておきましょう。
ちなみにIP₋PBXに接続する電話機はIPに対応しているため、電話機自体に内線番号を書き込めます。そのため移動先へ電話機を携帯すれば、どこでも同じ内線番号で通話したり、遠隔で電話機の設定を更新したりできます。
なおIP-PBXは「ハードウェア型」と「ソフトウェア型」の2種類に分類されます。
関連記事はこちら
ハードウェア型「IP-PBX」とは?
オフィス内にIP-PBX専用機器を設置して利用します。
【向いているケース】
- 保護された通信環境下で安全に利用したい場合
- 導入後に利用する機能を変更しない場合
ソフトウェア型「IP-PBX」とは?
ソフトウェア(IP-PBX機能)を自社サーバーへインストールして、ネットワークを構築して利用します。
【向いているケース】
- 事業規模の拡大や移転の予定がある場合
- 利用人数や拠点数が増加する見込みのある場合
- 接続するデバイスや機能を柔軟に選択したい場合
クラウドPBX(SaaS型)

クラウドPBX(SaaS型)は、インターネット上に構築されたPBXを利用するタイプになります。インターネット環境があれば利用できるため、主装置をオフィス内へ設置する必要がありません。小規模でも利用できるほか、スピーディな導入が可能なため、ベンチャー企業や新規事業などのスモールスタートに向いています。
それぞれの運営会社(ベンダー)が構築するPBXを利用するため、機能性やセキュリティ面などはインターネット環境と運営会社によって大きく差が出ます。またクラウドPBXもベストエフォートの回線を利用するインターネット経由の通話のため、通話品質は担保されません。
PBXでできる機能
ここでは、PBXを利用することでどのような機能を使えるかをご紹介します。

外線への発信制御
外線への発信制御には、基本的にLCR(Least Cost Routing)とACR(Automatic Carrier Routing)という2種類の方法があります。
LCR(Least Cost Routing)
LCRとは「最小のコストルーティング」を意味し、発信する相手の電話番号によって一番安いプロバイダを自動的に選択してくれる機能です。
発信時に特別な操作は必要なく、自動的に接続されるため、通話料を安く抑えられます。
ACR(Automatic Carrier Routing)
ACRとは「自動のキャリアルーティング」を意味し、設定済みの決められたプロバイダに自動接続される機能です。初期費用・通話料ともに、低価格に抑えて使用したい場合には最適と言えるでしょう。
LCRの方がお得に感じられますが、 LCRの機能を搭載したPBXは高額です。また外線の使用頻度が少ない場合にLCRを選択すると、通話料が高くついてしまうことがあります。
ちなみに昨今は通信キャリアのIP電話サービスを利用することで、全国一律料金で発信できます。そのため、そちらを収容できるひかり電話対応のPBXが人気です。
外線への着信制御
外線から着信を受ける場合、契約している電話回線の番号を親番号に設定し、同じ回線で共有しているその他の電話番号を子番号として紐づかせることによって、電話回線を有効活用できます。
ダイヤルイン機能
ダイヤルインとは、「ひとつの電話回線で複数の電話番号を利用できる」機能のことを指します。
ダイヤルインを使用しない場合、電話回線を契約している数に対して電話番号が振り分けられるため、電話機の数に応じた月額費用がかかってしまいます。
オフィスなど電話機をたくさん設置する環境では、ダイヤルイン機能を導入するメリットが大きいと言えるでしょう。
またダイヤルイン機能を使うことで、「取り次ぎコストの削減」というメリットも得られます。
顧客に渡す名刺にダイヤルイン番号を記載しておけば、相手からの着信を担当社員の端末で直接受けることができます。発信時に相手先へ通知されるのもダイヤルイン番号になるため、かけ直しの際でも取り次ぎ回数を減らすことができます。
内線同士の発信・着信
PBXに接続されている電話機同士では内線通話が可能です。内線化されている場合は同一回線での通話扱いになるため、通話料金が発生しません。
なお PBX に接続されていない電話機同士の場合は外線通話の扱いになるため、通話ごとに料金が発生します。
拠点間同士の発着信
事業規模が大きいために拠点が複数ある場合や、フロアが複数階に分かれている場合などは、それぞれの環境内にPBXを設置して専用回線で接続することができます。これにより遠隔でも内線通話が可能です。この場合の内線通話料金は発生しません。
代表番号着信機能
代表番号着信機能は、代表番号宛の着信をあらかじめ設定した登録先の電話機へつなげる機能です。相手先の電話番号に応じて、優先度が高い順につなぐ設定方法や、電話番号順につなぐ設定方法などがあります。
この機能を利用することで対応可能な部署へ直接電話を回せるため、効率よく業務を進められます。
ACD機能
ACD(Automatic Call Distributor)はコールセンターにおいて、受けた着信を自動で割り振る機能です。自動着信呼分配装置とも呼ばれます。
オペレーターの稼働状況やスキル、相手先の電話番号を地域や問合せ内容を考慮して、優先度が高い順に割り振ってつなぎます。
転送機能
転送機能にはさまざまな種類があります。転送機能を上手に活用することで、機会損失の低減や顧客満足度の向上につなげられます。
転送機能の種類
不在転送
担当者の不在時や繁忙時などの至急対応が難しい場合に、指定先の番号へ転送できます。
話中転送
着信時にその電話機が通話中であれば、あらかじめ設定済みの番号へ転送されます。
応答遅延転送
着信時、あらかじめ設定された呼び出し音の回数以内に応答できない場合、別の電話へ転送されます。
着信選択転送
定条件に該当する着信がある場合のみ転送されます。
圏外転送
モバイル端末(携帯電話・スマートフォンなど)を内線化して使用する場合に、圏外で対応が不可能であれば、サービス圏内にある他の電話へ転送されます。
パーク保留機能
通常の電話機で保留にする場合、通話を再開する時は同じ電話機を使わなければなりません。しかしパーク保留機能を利用すると、保留にした電話機以外でも通話を再開できます。
転送先が不明でも、的確な対応先を確認して情報共有後に別の電話で引き継げるため、スムーズな電話対応には欠かせない機能のひとつとなっています。
それぞれのPBXのメリット・デメリット

ここでは複数あるPBXのメリットとデメリットについてご紹介いたします。
レガシーPBX
レガシーPBXのメリット
- インターネット回線がなくても内線と外線を利用できる。
- 停電時にも利用できる。レガシーPBX内にバックアップ電源があり、接続されている電話機はPBXから供給される電源だけで動作する仕組み。
- 安定して動作するうえ、保守期間内であれば業者側がメンテナンスしてくれるため安心して利用できる。
レガシーPBXのデメリット
- 導入時のコスト、管理費用が高額になりやすい。
- 電話回線を利用するため、複数の拠点がある場合は内線を利用するために各拠点ごとにPBXの設置が必要。
- オフィスの移転や大規模なレイアウト変更や拡大などを行う際、設定変更にコストがかかる。レガシーPBXに接続する電話機の制御はすべてPBX側で行っているため、わずかな設定の変更作業であっても電設工事業者への依頼が必要。
ハードウェア型IP-PBX
ハードウェア型「IP-PBX」のメリット
- 専用機器を使用し、ネットワークを組織内で管理するため、稼働の安定性とセキュリティ面の安心感を期待できる。
- 専用機器を設置、接続してネットワーク構築を行えば使用できるため、短時間で環境設定が完了する。
ハードウェア型「IP-PBX」のデメリット
- 専用機器を設置している場所のレイアウトを変更したり、機能を追加したり、電話機を増やしたりしたい場合は、専用機器の移動や追加の作業が必要となる。
- 導入や交換時にかかる費用が高額になる傾向がある。
ソフトウェア型IP-PBX
ソフトウェア型「IP-PBX」のメリット
- 環境構築はソフトウェアのパッケージをインストールするだけのため、導入コスト削減につながる。
- インストール済みのソフトウェアをアップデートすることで、最新状態で利用し続けられるため、メンテナンスに関わる費用を削減できる。
- 機能の拡張や外部システムとの連携が簡単。
- 利用規模や回線などの増減もブラウザから設定できる製品が多いため、買い替えることなく利用できる。
ソフトウェア型「IP-PBX」のデメリット
- 自社サーバーが無い場合は、 IP-PBX を利用するために新しく用意する必要がある。
- ソフトウェアをインストール後、環境構築するための知識・技術を持つ人材が必要となる。また構築までに時間を要する場合がある。
- ハードウェア型よりセキュリティ対策に注意が必要。
クラウドPBX
クラウドPBXのメリット
- 導入や運用のコストを削減できる
- メンテナンスはサービス提供者側が行うため、運用に関する時間を割く必要がない。
- 事業規模の拡大・移転・拠点を増やす際にも柔軟に対応できる。
- 変更などの設定をすべてクラウド上で行える。
- 固定電話を設置する必要がなく、スマートフォンやパソコンを連携して従来の機能を利用できる。
- オフィス外でも代表番号を使って通話できる。
- 日本国内はもちろん世界中で内線通話が利用できる。
- CTI機能を使えるためスマートな顧客対応ができる。
クラウドPBXのデメリット
- 音質等、通話のクオリティがネット環境に左右されやすい。
- 緊急電話番号(110番・119番)への発信ができないため、緊急時の対応マニュアルが別途必要。※回線契約によってできる場合もあります
- 毎月の運用コストが必要になる。
- 電話番号はどこの場所にあるSaaSを使うかによって決まってしまう。たとえば九州にある会社が東京のSaaSを使用する場合、発信番号が03で始まる電話番号になることがある。
PBXと連携できる便利なサービス

CTI機能
CTI(Computer Telephony Integration)とは、コンピューターと電話の機能を連携させた技術やシステムの総称を指します。特に顧客対応のクオリティを向上させることに役立つ機能です。
CTIには主に「ポップアップ機能」「CRM連携機能」「通話録音機能」という3つの機能があります。
ポップアップ機能
顧客からの着信を受ける際、着信中の電話番号をもとに顧客の情報を検索し、担当オペレーターのパソコンに表示する機能です。通話中に必要な情報を検索・閲覧が可能なので、対応がスムーズになり業務効率アップにつながります。
CRM連携機能
CRM(Customer Relationship Management)機能は、主にコールセンターなどで活躍します。顧客の対応履歴(過去に対応した内容や担当者)について詳細な情報を管理するシステムと連携し、担当オペレーターが適切に対応できるようにサポートするのです。
またCRMには過去の対応履歴で蓄積されたデータをもとに、「データ分析」や「ターゲット化された情報抽出」といった、効率よくマーケティングに活用できる機能も搭載されています。
なお昨今は、電話やメール以外のコミュニケーションツールを利用する人が増えていることから、LINE・チャット・SNSなど、多様なツールとの対応履歴についても一元管理できる機能が活用されています。
通話録音機能
必要に応じて、顧客との通話内容を録音・再生・削除できる利点があります。
クレーム対応時やオペレーターの電話対応技術向上の研修に利用することも可能です。
コミュニケーションツール連携機能
一部のPBXベンダーの製品は、Microsoft(マイクロソフト)提供のコミュニケーションツール「Teams」やチャットツール「Chatwork」「Slack」などとの連携に対応しています。
こういった電話機能以外のツールをPBXと連携することで、従来使用してきた電話番号や電話機を活用しながら、多様なコミュニケーション方法を取り入れられるようになるのです。
特にオフィス外の場面において、発着信や転送といった取り次ぎをスムーズに行えるようになります。お互いの稼働状況などもアプリを通して共有しやすくなるため、上手く活用することで業務効率アップや経費の削減にもつながるでしょう。
在宅勤務は今後さらに増えることが予想されます。自社の働き方に合うPBXベンダーの選択が必要です。
PBXの選び方

これまでPBXの種類やビジネスフォンとの違い、各種メリット・デメリットなどについて解説してきました。
どのPBXが自社に適しているのかは、事業規模や職種、働き方などによって優先するポイントが異なります。ここでは導入時または買い替え時に確認すべきポイントを、5つの項目にまとめて紹介します。
①設置する環境
PBXは使用環境の規模に応じて適したものを選ぶ必要があります。まずはPBXの導入を検討している組織の規模感を把握しましょう。
確認するのは主に以下の点です。
- 事業規模
- 従業員数
- 拠点数(国内・海外を含め)
- フロア数
- サテライトオフィスの有無
またこれらとあわせて、職種や業務内容の確認も必要です。
- 外線を利用する状況と頻度
- 内線を利用する状況と頻度
- 対外的な利用(例:顧客対応など)と組織内部での利用の割合と内容
- オフィス内で電話を利用する人数
- 在宅勤務や、外出先(営業など)で電話を利用する人数
働き方や仕事内容にはさまざまな種類があり、同じ組織の中でも担当する業務内容によって異なる場合があります。オフィス内での業務中心であればオンプレミスPBX 、オフィス以外の環境で行う業務が中心であれば柔軟に対応できるクラウドPBXが向いているとされています。
②機能性
機能性の部分は、実際の業務内容や業務効率に直接関わる部分です。自社の業務に必須となる機能を漏れなく洗い出し、改善点も含めて徹底的に検討するのがよいでしょう。
スマートフォンやタブレット端末の接続、アプリケーションの活用などを検討している場合は、クラウドPBXの導入が向いているとされます。
自社の働き方がどのようなものになるのかを視野に入れた選択が必要です。
③拡張性
拡張性はスケーラビリティ(scalability)とも呼ばれ、「設置する環境」や「機能性」の部分に関わる項目です。
- 将来的に事業が成長・拡大する見込みがあるか?
- 拠点数・オフィスの規模を拡大する予定があるか?
- 移転の可能性があるか?
- 今後の企業活動をどのように展開するのか?
上記のようなポイントをチェックする必要があります。
PBXの導入を検討する段階で何かしらの変化が見込まれる場合は、拡張性の高いPBXを選択しましょう。
クラウドPBXはオンプレミスPBXに比べ拡張性が高いと言われていますが、クラウドPBX自体もサービス提供者によって特徴は異なるため、自社が求める拡張性をしっかり確認して適切な選択をすることが大切です。
④費用
費用面について検討する際は、導入・買い換え時の初期費用に加えて、以下のような長期的にかかる費用も見積もる必要があるため、現実的に運用可能かどうか確認しましょう。
- 維持費
- メンテナンス費(それに関わる人件費)
- 備品購入費
- 次回買い換え時の費用(オンプレミスPBXの場合)
クラウド PBX は初期費用を抑えられると言われていますが、月額または年額の定期的な運用コストは必要です。また利用する人数によっても金額が変わってくるため、大企業の場合は割高になる可能性もあります。
組織によってはオンプレミスPBXの方が費用を抑えられるケースもあるため、そういった部分を加味した上で、比較検討することをおすすめします。
⑤セキュリティ面
セキュリティ対策はPBXに限らず、企業活動を行う上で重要な課題のひとつです。
インターネットに接続している状態というのは、常にセキュリティの脅威と隣り合わせであることを意識しなければなりません。PBXを利用するうえでは、下記のような懸念点が挙げられます。
- 乗っ取りやなりすましなどによる不正利用、データ改ざん
- サイバー攻撃の脅威
- 何らかの原因によるデータ流出
PBXは組織の重要な情報を扱う手段となるものです。導入を検討する際は、可能な限り、強固なセキュリティ構築を優先するとよいでしょう。
強度の高いセキュリティを重視する場合は、独自の利用環境を構築できるオンプレミスPBXが最適と言われています。
クラウドPBXのようにインターネットを介してPBXを利用する場合は、強固なセキュリティが備わった信頼できるベンター
- どのような運用をしているのか?
- どのようなサポート体制なのか?
- セキュリティ対策に関して過去にどのような対処を行ってきたか?
などの項目についてよく確認し、比較検討することをおすすめします。
なおクラウドPBXを利用する場合、回線契約によっては、緊急電話番号(110番・119番など)に発信できないことや停電・災害時などに使用できなくなることも忘れてはなりません。
まとめ
この記事を読んで、「実はPBXが身近にあった」と気付いた方もいるのではないでしょうか。
PBXは自社に合うものを選択、導入することが何より重要です。新規導入を検討されている方だけでなく、既存のPBXユーザーの方も、ニューノーマルなビジネスや働き方にフィットするコミュニケーション方法を実現させるために、PBXの活用方法を見直してみてくださいね。
執筆・監修者
- カテゴリ:
- PBX