更新日:
公開日:
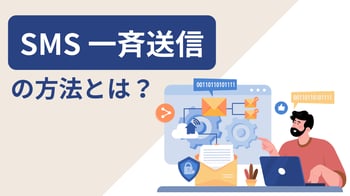










BLOG
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ
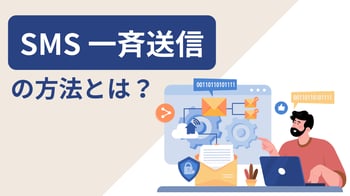
近年、企業の情報発信手段は多様化していますが、「開封率の低さ」「メールの埋もれ」「メール送信にかかる手間」など、顧客コミュニケーションにさまざまな課題を感じている企業も少なくありません。そんな中、シンプルかつ確実に情報を届けられる手段として活用されているのがSMS(ショートメッセージサービス)です。
SMSは携帯電話番号さえわかれば送信できることから、本人確認・認証コードの送信、リマインド通知、キャンペーン告知など、さまざまな場面で活用されています。また多数の顧客に効率的に情報を届けたい場合は、「SMSを一斉送信する」ことが有効な方法として挙げられます。
本記事では、SMSを一斉送信する具体的な方法やメリット、注意すべき点、サービス選択のポイントを詳しく解説します。効率的かつ効果的な情報発信の方法をお探しの方はぜひ参考にしてください。

SMSでは、多数の相手に対してメッセージを一斉送信できます。効率的に情報を伝えられるため、さまざまなビジネスシーンで活用されています。中でも代表的な用途は以下のとおりです。
SMSといえば、携帯電話に標準搭載されている機能を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに携帯電話のSMSでも複数の宛先にメッセージを送信できますが、端末によっては1日の送信件数に制限があり、大量送信には不向きです。また履歴の管理や送信結果の確認など、ビジネスで求められる機能が備わっていない点も課題と言えます。
そのため、ビジネス目的でSMSを一斉送信するには、法人向けのSMS配信サービスを活用するのが効果的です。法人向けのSMSサービスであれば、企業が多数の送信先へSMSを配信する前提の設計となっているため、管理画面やAPIを通じて複数宛先への一斉送信を実現できます。送信先情報はCSVやExcelで一括登録できるため、事前のリスト準備もスムーズに行えるでしょう。
さらに、国内キャリア網を経由して高い到達率を確保できるサービスや、自社の顧客管理システムと連携できるAPI連携型のサービスもあります。

SMSを一斉送信を活用することでどのようなメリットを得られるのか、具体例を見ていきましょう。
顧客の携帯電話番号に直接送信されるSMSは、到達率や開封率が高く、一斉送信することで大量の顧客に効率的に情報を届けられます。
たとえばメールの場合、顧客側が複数のアドレスを使い分けているために届いているメールに気付かないケースや、アドレス変更によりそもそもメールが未達になってしまっているケースが往々にしてあり得ます。
しかし携帯の電話番号は、一度取得したら以降は機種変更があっても変わらない場合がほとんどです。そのためSMSであれば、より高い確率で顧客本人にメッセージを届けられます。また顧客はSMSのプッシュ通知をオンにしていることが多いため、メッセージが届いた際にすぐに気づいてもらえます。さらに、SMSは迷惑メールフォルダに振り分けられることも少ないため、高い確率でメッセージを開封してもらえる点も特徴です。
総務省の「令和6年版 情報通信白書」によれば、2023年のスマートフォン世帯保有率は90.6%。広く普及しているうえ、24時間365日いつでも手元に置いているデバイスであることから、よりSMSに気付いてもらいやすいと言えます。
こうした特性から、キャンペーンやリマインド通知など、大量の顧客へ迅速に情報を届けたい場面では、SMSのように確実に届きやすい媒体で一斉送信することが大きな効果を発揮します。
SMSは電話番号さえあれば送信できるため、他の手段と比べて導入・運用のハードルが低いというメリットがあります。
たとえば電話はオペレーターによる個別対応が必要になり、郵送は印刷・封入・郵送料などのコストが発生します。メールは迷惑メールフォルダへの振り分けや開封率の低さが課題となっており、文面調整や再送業務といった手間が生じるケースも少なくありません。
一方、SMSであれば送信先のリストはCSV形式で一括管理でき、管理画面から簡単にアップロードして複数人へ同一メッセージを配信することが可能です。1通あたりの送信コストは数円〜十数円程度かかるものの、到達率・開封率の高さを踏まえると費用対効果に優れていると言えるでしょう。
SMSはスマートフォンや携帯電話に標準搭載されている機能です。そのため、受信者側で特別なアプリのインストールやアカウント登録を行う必要がありません。誰もが使える機能のため、ITリテラシーの有無や年代に影響されないのが強みです。
たとえば自社アプリを通じてメッセージを送る場合、アプリをインストールしてもらえなければ情報を届けられず、機会損失につながります。しかしSMSであれば初期設定が不要なため、あらゆる層の顧客との接点を広げることが可能です。
このように、誰でも利用できる媒体であるため一斉送信との相性が良く、ターゲット全体にまんべんなく情報を届けられる点もメリットです。SMS一斉送信は、幅広い顧客層を抱える企業にとって、確実性と効率性を兼ね備えたアプローチ手段となります。

SMS一斉送信を効果的に活用するためには、いくつかの注意点を踏まえておく必要があります。あらかじめ意識しておくことで、トラブルを回避した、より良い配信結果が得られるでしょう。
SMSには文字数の制限があるため、送信内容を簡潔にまとめる工夫が必要です。機種やキャリアによって上限は異なりますが、一般的には全角670文字・半角1,530文字までとなっています。
また古い機種や一部端末では、全角70文字・半角160文字が上限になるケースもあります。上限文字数を超えてしまうとメッセージが複数に分割されて届くため、読みづらくなったり、意図が正しく伝わらなかったりする可能性があります。
特にキャンペーン通知やリマインドなど、ビジネスにおいて確実に伝えたい内容がある場合は、文字数を意識してメッセージを設計するようにしましょう。
SMSは基本的にテキストのみの通信手段であり、画像や動画などのメディアファイルを直接添付できません。(※iPhone同士でのiMessageなど一部例外を除く)そのため商品の写真を添えて案内したいキャンペーン通知や、動画で説明したいサポート連絡などには不向きな面があります。
対処法としては、画像や動画を掲載したWebページを用意し、そのページの短縮URLをSMS本文に記載して誘導する方法が挙げられます。テキストの中で視覚情報に誘導する工夫を加えることで、SMSでも充分な情報伝達が可能になるでしょう。
SMSで広告や宣伝などのメッセージを配信する場合は、「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」を遵守する必要があります。
特定電子メール法では、「事前に同意を得た受信者にしか商業メッセージを送ってはいけない」と定められています。違反した場合は業務停止命令や罰則の対象となる可能性があるため、注意しましょう。
法令違反を未然に防ぐためにも、以下の4点を確実に実行することを心がけてください。
トラブルを未然に防ぎ、安心してSMSを活用するには、法令の遵守が何より大切です。
SMSは、すぐに相手にメッセージを届けられる便利なツールです。しかし送信タイミングによっては、相手に悪印象を与えかねない点に注意しなければなりません。
たとえば深夜や早朝にメッセージを送信すると、受信者にストレスを与えてしまう可能性があります。自社ビジネスの業種や顧客層に合わせて、最適な時間帯を選ぶようにしましょう。
また毎時00分(例:12:00、15:00など)は多くの企業がSMSを送信する時間帯のため、通信が混み合いやすくなったり、ほかの企業のメッセージに埋もれてしまったりする場合があります。メッセージを確実に届けたい場合は、送信時間を分散させる工夫が有効です。

SMSを一斉送信できるサービスには数多くの選択肢があります。効果的に活用するためには、自社にあったサービスを選ぶことが欠かせません。ここではどのようなポイントを押さえておくべきかをご紹介します。
SMSの配信方式には、大きく分けて「国内直収型」と「国際網経由型」の2種類があります。
国内直収型は、日本の携帯キャリアと直接接続して配信する方式です。到達率が高く、キャリアの迷惑メールフィルターにもかかりにくいのが特長です。
一方で国際網経由型は、コストを抑えられるケースがあるものの、スパム判定や受信ブロックのリスクがあります。
重要な情報を確実に届けたいなら、国内キャリア網を利用できるSMS配信サービスを選ぶのがおすすめです。
SMS一斉送信サービスを選ぶうえで、費用対効果は重要な比較ポイントです。
多くのサービスでは、実際にメッセージが配信された分だけ料金が発生する「従量課金制」が採用されています。従量課金制は、1通あたり10円前後が相場です。配信件数が多い場合には、ボリュームディスカウントが適用され、単価がさらに下がるケースもあります。
ただし、サービスによっては月間の最低送信数や基本料金が設定されていることもあります。そのため、総コストの見積もりは事前に確認しておくことが肝心です。
一度に数千件〜数十万件規模のSMSを配信する場合は、送信可能な件数に加えて、処理速度や配信の安定性も確認すべきポイントです。配信件数が多いほど、遅延や送信失敗が発生しやすくなります。
実績のある配信基盤を持つサービスを選ぶことで、大量のメッセージを確実かつスムーズに配信できるようになります。
SMS配信サービスを選ぶ際は、ユーザーからの返信を受け取れる「双方向対応」が可能かどうかもチェックしておきましょう。
一方通行の配信だけでは、確認・予約・問い合わせなど、顧客とのコミュニケーションが必要な場面には対応できません(顧客からの回答を受け付けるため、予約サイトのURLを記載するといった工夫が必要になります)。双方向でコミュニケーションが取れれば、顧客とのやり取りをよりスムーズにし、サポート業務の効率化やエンゲージメント向上にも役立つでしょう。
導入前に、返信可否や受信方法について確認しておくことが望ましいです。
SMS一斉送信は、高い到達率と開封率を誇る効果的なコミュニケーション手段として、多くの企業に活用されています。ただし文字数制限や法的要件など、注意すべきポイントもあるため、適切なサービス選択と運用が成功の鍵となります。
「Vonage SMS/Message API」では、秒間30通の大量送信が可能で、国内直収ルートの送信もできるため、海外経由のSMSに比べてより高い開封率が期待できます。双方向のやり取りも可能で、SMSだけでなく、その他のコミュニケーションツールとの連携も可能です。
効果的なSMS一斉送信の実現には、信頼性の高いサービスの活用をおすすめします。