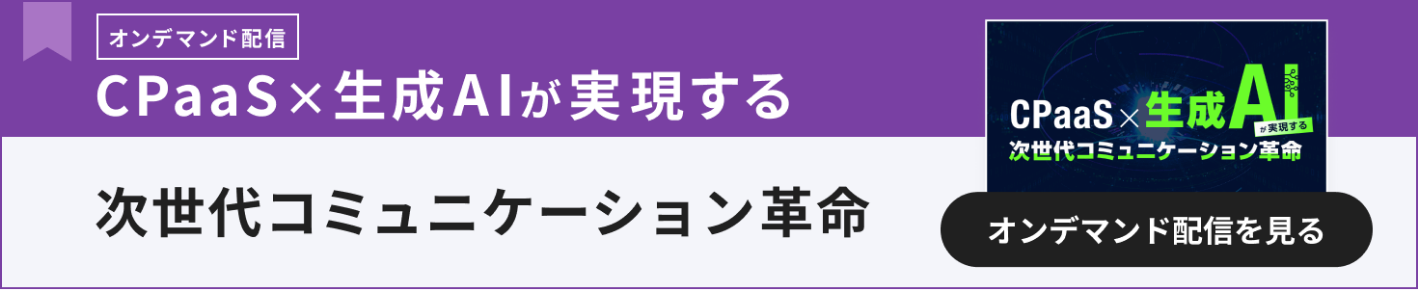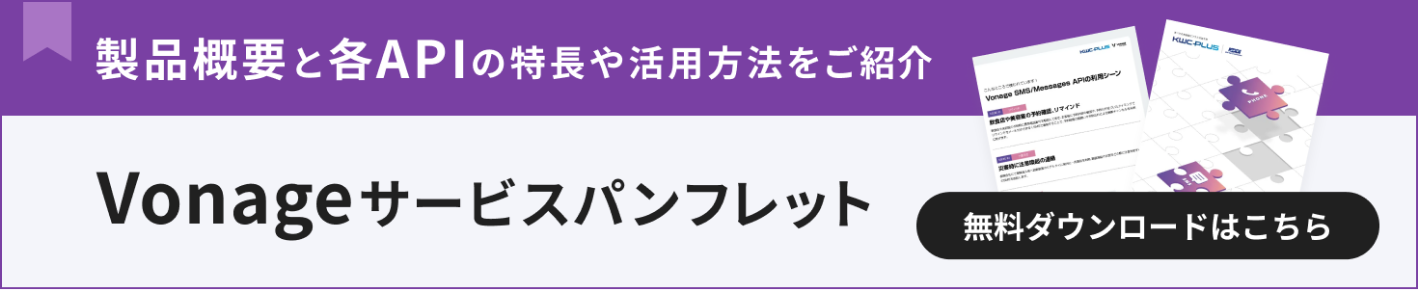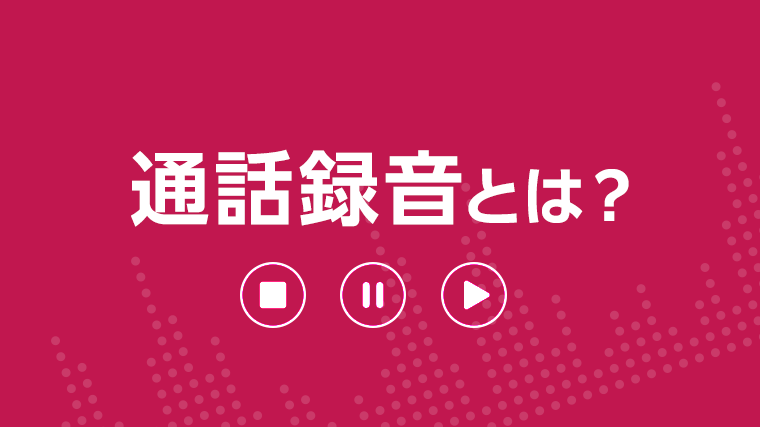オートコールとは?活用するメリットや導入がおすすめの企業について解説
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ

顧客対応の現場では、電話対応にかかる時間やコストの削減、業務の効率化が求められています。そこで注目されているのが、あらかじめ設定した電話番号に対して録音済み音声を一斉に自動発信できる「オートコール」という仕組みです。
オートコールは、顧客対応や業務効率化を目的として幅広い業界で利用されています。その設計や運用次第では大きな価値をもたらしますが、適切な設定と使用が重要です。
この記事では、オートコールの概要や仕組み、活用するメリットについて詳しく解説します。
オートコールとは

オートコールとは、あらかじめ設定した顧客リストに対して、録音済みの音声を自動で一斉発信できる機能のことです。
音声データをシステムに登録し、送信先のリストや発信タイミングを指定することで、人手を介さず効率的な架電が可能となり、営業・督促・案内業務などの負担軽減につながります。
さらに、自動音声応答(IVR)と組み合わせることで、顧客のプッシュ操作に応じた部署への転送や内容に応じた案内の出し分けも可能です。このような機能を提供する仕組みは「オートコールシステム」と呼ばれ、幅広い業種・業務で導入が進んでいます。
関連記事はこちら
オートコールシステムの導入メリット

オートコールシステムの導入は、コールセンター運営においてさまざまなメリットをもたらします。具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。
アウトバウンド業務の効率化につながる
オートコールシステムの導入により、膨大な量の架電リストでも一度に電話をかけられます。オペレーターが架電する場合と比較すると、アウトバウンド業務の大幅な効率化が可能です。
また「電話をすぐに切った」、「音声ガイダンスに沿ってボタンを操作した」など、電話をかけた相手の行動を把握できるため、見込み客を特定する際にも役立ちます。
さらに、オートコールシステムは日時や曜日を指定した発信も可能です。対象とする顧客の行動傾向を把握していれば、電話がつながりやすい時間帯や曜日を狙って架電できます。
サービス品質を一定に保ちやすい
オートコールシステムは、事前に設定・録音した音声をそのまま流す点が特徴です。そのため、オペレーターのスキルや経験によってトーク内容が変わるといった属人化が発生しません。
膨大な量のリストに電話をかける場合でも、顧客一人ひとりに合わせて個別の内容を録音する必要はありません。発信される案内はすべて同じ内容となるため、一定レベルでの電話対応ができ、サービス品質を一定に保てます。またオートコールシステムなら、電話に出た相手の感情や気分、回答内容に惑わされることもありません。不要な情報にとらわれず、常に必要な質問が可能です。
オペレーターと顧客、双方の負担を抑えられる
コールセンターをはじめとした電話対応では、ぶっきらぼうな対応、即切り、会話の引き延ばしなど、さまざまな要因でオペレーターが負担を感じてしまう場合があります。
オートコールシステムの場合、電話の発信から応答、案内までの流れをシステムが対応します。案内に興味を持つ人のみをオペレーターへと転送するため、オペレーターの精神的負担が和らぐのがメリットです。
また、顧客側の負担軽減につながるのもポイントです。アウトバウンド業務では、興味のない話を聞かされたり、オペレーターが一方的に話をしたりと、顧客がストレスを感じることがあります。しかし録音の音声を使用したオートコールシステムであれば、案内に興味がないと感じた時点で通話を終了できるので、顧客の負担軽減にもつながるでしょう。
人件費の削減につながる
大規模なコールセンターでアウトバウンド業務を行うようなケースでは、1日に数多くの架電が必要です。その分オペレーターの人数も多くなり、人件費の増加につながります。
オートコールシステムがあればオペレーターが架電業務を担う必要がありません。また有人対応に切り替える場合でもオペレーターの業務量を減らせます。これにより確保すべき人員が減り、人件費の削減につながるでしょう。
オートコールシステムの活用が効果的なシーン

オートコールシステムの活用が特に効果的なシーンについて、どのようなものがあるのか具体的に解説します。
テレアポをはじめとする電話での営業活動
テレアポをはじめとした電話での営業活動は、オートコールシステムの代表的な活用シーンのひとつです。これらの活動では、以下のような課題が生じがちです。
- オペレーターが精神的な負担を感じやすい
- オペレーターによって対応に差が出やすい
- 教育を行っても、スキルの差が解消されない
しかし架電業務をオートコールシステムが担うことで、一次案内は音声ガイダンスが、その後興味を示した顧客のみオペレーターが対応するというフローを構築できます。これにより、オペレーターの属人化の問題も解消しやすくなるほか、精神的な負担軽減にもつながります。
督促業務
オートコールシステムは督促業務でも活用され、提出期限切れの書類、返却期限を超えたレンタル品、未払い料金などを回収する際に役立ちます。
督促業務はその性質上、オペレーターの心理的負担が大きくなりやすいという特徴があります。そもそも電話がつながりづらい、という特徴もあり、営業時間外に折り返しがあるケースも珍しくありません。そのため、組織全体の生産性の低下につながります。
オートコールシステムは、電話がつながりやすい時間帯を指定し、人手を介さずに案内が可能です。さらに、自動音声で営業時間を案内できるため、生産性低下のリスクを抑えられます。
アンケート調査
オートコールシステムは、満足度調査や世論調査といったアンケートにも活用が可能です。
本来、電話によるアンケート調査は多くの人に電話をかける必要があり、一人ひとりに口頭で対応しなければならないため、どうしても手間がかかります。オートコールシステムなら、アンケートの案内から回答の収集まで、一連の作業を自動化できるため、大幅な効率化が見込めます。
また、オペレーターの言い回しによって回答が左右されるリスクを回避できるのも利点です。方法次第では、オペレーターが案内するよりも正確な調査結果を収集できるケースもあります。
予約確認
美容室やエステ、クリニックなど、電話で予約確認を行うケースでもオートコールシステムの活用が可能です。
サービスの予約確認では、数ヶ月先に予約した場合などに、顧客が予約したことを忘れてしまうケースもあります。オートコールシステムを利用して、予約日が近付いたタイミングでリマインドの電話をかけるフローを構築すれば、予約忘れやドタキャンといった機会ロスを防ぐ効果が期待できます。
わざわざ有人対応せずとも済むため、オペレーターの心理的ハードルを下げられるのもメリットです。
安否確認
高齢者への安否確認や災害時のアナウンスなど、非常時においてもオートコールシステムの活躍が期待できます。
安否確認は、地方自治体の職員や介護職員が電話をかけて、高齢者の様子や体調をうかがうのが一般的です。毎日複数人にかけることもあり、手間がかかるうえに、かけ忘れや間違い電話などのヒューマンエラーが起こる可能性も生じます。
オートコールシステムなら、事前に設定した日時に架電できるのはもちろん、電話に出たか否かといった情報も把握しやすいです。プッシュボタンで操作できるアンケート形式のものにすれば、高齢者の状況を把握するのにも役立ちます。
オートコールシステムを導入すべき企業

オートコールシステムは、単なる自動発信の仕組みではなく、現場の「ムダ」や「人手不足」、「業務の属人化」といった課題を解消する手段として注目されています。
とくに、以下のような悩みを抱える企業では、導入を積極的に検討する価値があります。
- 複数の電話番号に対して日常的に架電が発生する企業
- オペレーターの精神的・肉体的な負担を軽減したい企業
- 限られた人員で営業・案内・調査などを行っている企業
- 業務効率化によって人件費や稼働コストを抑えたい企業
- 定期的な通知やリマインド業務によってコア業務が圧迫されている企業
また、従来は人の手で行っていた業務も、オートコールシステムを活用することで自動化・効率化が可能になります。現場の負担を軽減し、限られたリソースを最大限に活かすためにも、自社の課題と照らし合わせて導入を検討すると良いでしょう。
オートコールの導入事例

選挙支援サービス『知るフォン』を展開する株式会社ターゲットリサーチでは、選挙期間中に必要となる大量の架電業務を効率化するため、オートコールシステムを導入しました。
従来は短期間に数万件以上の電話を発信する必要がありましたが、通話料が高く、コスト面で大きな課題を抱えていました。そこで同社は、CPaaS「Vonage」を活用し、オートコールとクラウドPBXを組み合わせた柔軟なハイブリッド運用を実現しています。秒課金制により最大40%のコスト削減を見込みつつ、安定した通話品質も確保できました。
また、日本語でのサポート対応や、スピーディな実装(約1.5ヶ月)も導入の決め手となりました。同社では今後の事業展開として、音声通知だけでなくSMS配信や動画連携など多チャネル化も検討中です。オートコールの活用により、業務効率とコスト最適化の両立を図った好例といえるでしょう。
オートコールシステムを導入する際の注意点

オートコールシステムを導入する際は、いくつか注意すべき点があります。ここではオートコールシステムならではの課題と、その対策について見ていきましょう。
臨機応変な対応が難しい
オートコールシステムでは自動音声で対応するため、どうしても機械的になり、人間のような臨機応変な対応がしにくい側面があります。
この問題の対策は、事前に細かなシナリオを用意しておくことです。さまざまなケースや回答を想定したシナリオを作成することで、完璧ではなくとも、ある程度のパターンには対応できるようになります。また有人対応へ切り替えられるようなルート設計も併せて行っておくと、無人対応ではどうしても難しいときでもスムーズに解決できるでしょう。
相手に警戒心を与える可能性がある
顧客によっては、電話に出た瞬間から自動音声による案内が始まるという状況に違和感を覚える場合もあります。どれほど高品質なシナリオを作成していても、機械音声の不自然さや人工的な響きに警戒心を持ってしまい、「早くオペレーターに切り替えてほしい」と考える顧客もいるでしょう。場合によっては途中で電話を切ってしまう可能性もあります。
したがって、オートコールシステムのシナリオを作成する際は、要点をできるだけ簡略的にまとめることが重要です。そのうえで、プッシュボタンの操作によってオペレーターにつながることを訴求できるとなおよいでしょう。
オートコールシステムの比較ポイント

オートコールシステムは、以下のようなさまざまな観点から比較することが大切です。どのような点を意識して見ていくべきか、ポイントをいくつか紹介します。
最大コール数
最大コール数とは、1回の架電で同時にコールできる数のことです。コールセンターの規模や業務内容によっては、1日に数千件や数万件の架電が必要になるケースもあります。しかしシステムが対応できる最大コール数が少なければ、このような数を処理しきれません。
特にアンケート調査などでオートコールを利用する場合、母数のサンプル数が多ければ情報の精度が高まりやすいため、同時コール数の多さが重要な要素になります。製品によって最大コール数は異なるため、架電リストをもとに適正な量を把握しましょう。
音声のバリエーション
オートコールサービスの製品によって、利用される自動音声もさまざまです。あらかじめ用意されている人工音声によってアナウンスを行うものもあれば、自社の従業員の声を録音して流すように設定するものもあります。
声のトーンや話し方のテンポは、顧客がすぐに電話を切らずにいてくれるかどうかを左右する重要なポイントです。自社のブランドイメージや顧客の属性なども考慮しつつ、適切な音声パターンを備えた製品を選びましょう。近年ではAIを活用した、人工音声でありながら限りなく人間の肉声に近い自然な音声も少なくありません。また製品によっては、プロの声優やナレーターの音声を利用できるものもあります。
分岐・転送の設定方法
オートコールシステムでは、有人対応に切り替える際に分岐や転送が必要です。そのため製品を選ぶ際は、分岐や転送をどのように設定できるか確認しましょう。細かい設定内容を理解するために、無料トライアルを申し込むのも1つの方法です。また、サービス提供事業者から設定内容のアドバイスをもらえる場合もあるので、不安な場合は事前の相談をおすすめします。
オートコールにおいて、「スムーズに分岐するか」「適切な担当オペレーターへ電話がつながるか」はアンケートの回答率やアポ獲得率にも影響します。細かい部分にも着目して、自社の要件を満たせるサービスや製品を探しましょう。
SMSとの連携可否
オートコールサービスには、発信した電話の内容をSMSで送信できる機能があります。
たとえば未払金の督促をオートコールで行う場合、最初に電話案内を行ったのち、SMSで金額や振込先といった詳細情報を送るといったことが可能です。これにより、顧客は確認のために電話をかけ直す必要がなくなります。電話とSMSを組み合わせることで成約率が高まるようなケースには、特に求められる機能だと言えるでしょう。
ただしSMSと連携できるかどうかは製品によって異なります。検討時に事前確認しておきましょう。
関連記事はこちら
料金体系
オートコールシステムの料金体系を確認する際は、自社の運用状況に合ったプランを選択することが大切です。
料金は、一般的に「月額固定制」、「1コール接続ごと」、「通話時間ごと」の3つに分かれます。架電数や通話時間が少ない場合は通話時間制がコストを抑えやすい一方、頻繁に使用する場合は月額固定制が適していることもあります。
サービスごとの条件や料金設定に差があるため、一日の架電数や通話時間をもとに比較し、自社に最適なプランを選びましょう。
おすすめのオートコールシステム・サービス
ここでは、オートコールシステムの導入を検討されている方へ向けて、おすすめのサービスをご紹介します。
Vonage Voice API
Vonage Voice APIは録音や音声認識、IVRなど、通話に必要なあらゆる機能をプログラムでコントロールできるAPIです。
世界中の電話番号を用いたPSTN(公衆回線網)やSIP、Web RTCでの発着信機能を利用できます。これにより従来の固定電話だけでなく、スマートフォンやPCでも発着信を行えるようになるため、物理的な機器や回線を用意するコストがかかりません。
また外出先や自宅からでも電話業務を行えるため、BCP対策としても役立てられるでしょう。
また実際にVonage Voice APIを利用して、1日数万件の自動発信を実現するオートコールシステムを構築した企業の事例もございます。ぜひこちらも併せてご覧ください。
まとめ
オートコールシステムは、業務負担の軽減やサービス品質の均一化、人件費の削減といった課題にも対応可能であることから、近年ではさまざまな業種で活用が進んでいます。一方で、システムによって特徴や機能が異なるため、自社の業務内容や解決したい課題に合わせて、最適なシステムを選定することが重要です。
オートコールシステムを導入するなら、KDDIウェブコミュニケーションズが提供する「Vonage Voice API」がおすすめです。音声合成の性別やアクセント調整、IVR分岐設定など柔軟な設計が可能で、実践的な機能を備えています。電話業務の効率化を目指す企業の方は、導入をぜひご検討ください。
執筆・監修者
- カテゴリ:
- 電話 DX