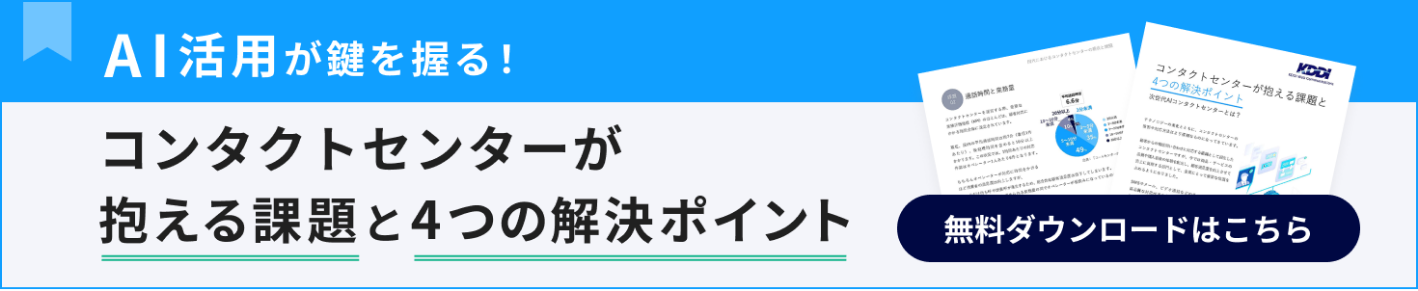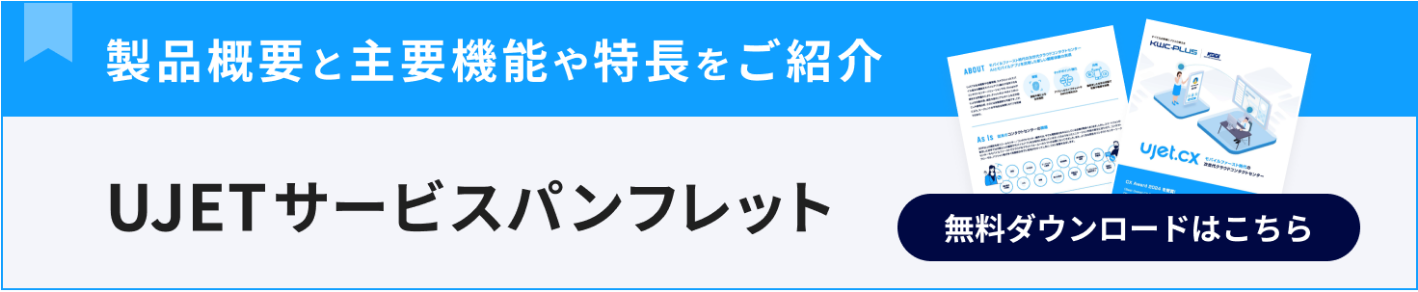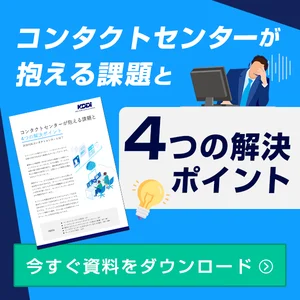ボイスボットとは?IVRとの違いや導入メリット、注意点を解説
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ

昨今、多くのコールセンターが顧客対応の効率化や自動化についての課題を抱えています。そこで注目されているのが、AIを活用した「ボイスボット」です。
この記事では、ボイスボットの概要や仕組み、IVR(音声自動応答システム)との違いについて詳しく解説します。ボイスボットの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ボイスボットとは

ボイスボットとは、音声認識AIがオペレーターの電話業務を代行するシステムのことを指します。人間の音声を自動認識し、その音声にもとづいた電話対応を行うことから、電話の自動応答システムの一種とも言えます。
ボイスボットは顧客からの問い合わせ対応や予約受付などのインバウンド業務に用いられることが多いです。ただし製品によってはアウトバウンド業務に対応できるものもあり、一人暮らしの高齢者を対象とした見守りサービスや予約確認のリマインドコールなどで活用されています。
関連記事はこちら
ボイスボットとIVRの違い
IVRは「Interactive Voice Response」の略語で、自動音声応答システムのことです。顧客からの電話に対して、事前に設定した音声案内を自動再生することにより、問い合わせ内容に適したオペレーターやサービスに接続できます。
あらかじめシナリオを設定しておくという点ではボイスボットと同じですが、IVRの場合はあくまで決められた音声ガイダンスを流すだけで、顧客からのプッシュ信号がなければ次のフローへの案内を行いません。そのため「プッシュボタン操作をするために、長い音声案内を最後まで聞かないといけない」といった状況が起こりやすく、顧客にストレスを与えてしまう場合があります。
一方でボイスボットは、AIが顧客の会話内容をリアルタイムで解析して、その内容に適したシナリオに沿って会話形式で手続きを進めます。リアルタイムでのコミュニケーションが可能なため、顧客にかかるストレスを軽減できるのです。
関連記事はこちら
ボイスボットとチャットボットの違い
チャットボットとは、顧客とテキストメッセージで自動的に会話やコミュニケーションを行うシステムです。
特定の処理を自動で行う点はボイスボットもチャットボットも共通していますが、チャットボットの場合はテキストで顧客とコミュニケーションを取ります。そのためパソコンやスマートフォンの画面上で、文字だけのやり取りが必要です。問い合わせ内容が複雑で、顧客側で状況説明をうまく文章に起こせない場合には、最適な案内ができない場合もあります。
一方でボイスボットは、基本的に音声でやり取りします。利用するチャネルも電話のみです。また問い合わせ内容をAIが解析するため、顧客の自由な話しぶりにも適切に対応することが可能です。
ボイスボットの仕組み
ボイスボットの仕組みは、受電してから顧客に回答するまでの流れを理解するとわかりやすいです。
|
1 |
入電の感知 |
顧客からの電話を感知し、事前に設定されたシナリオをもとにボイスボットが受電 |
|
2 |
発話による問い合わせ |
ボイスボットの案内に沿って、顧客が問い合わせ内容を発話によって回答 |
|
3 |
発話内容のテキスト化 |
ボイスボットが発話内容を即座にテキスト化 |
|
4 |
AIによる回答の検出 |
テキスト化した情報をデータベースで検索し、問い合わせ内容に適した回答を検出 |
|
5 |
回答の読み上げ |
検出された回答を再びテキスト化し、音声合成技術によってボイスボットが回答を読み上げる |
ボイスボットはAIによる学習機能(機械学習)を搭載しており、与えられた複数のデータ同士の関連性や法則性を見つける作業を繰り返し自動的に行えます。つまり人間のオペレーターと同じように、顧客との会話経験を積めば積むほど回答の精度が増す<のです。その結果、人間の学習能力と似た判断作業を行えるようになります。
ボイスボットを導入するメリット

ボイスボットの導入により、電話対応の効率化やオペレーターの負担軽減、人件費の削減、顧客満足度の向上、機会損失の回避など、さまざまなメリットが期待できます。
ここからは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
電話対応の効率化につながる
ボイスボットは、問い合わせ内容を認識したうえで顧客の発話を解析できます。必要に応じて回答やシナリオを追加することも可能です。つまり簡単な問い合わせやよくある定型的な質問であれば、ボイスボットだけでも充分に対応できます。
これによりオペレーターは、有人対応が必要な問い合わせや電話対応以外の業務に注力できるようになるのです。
オペレーターの負担を抑えられる
人手不足が叫ばれて久しいコールセンター業界で、オペレーターは日々寄せられる大量の問い合わせに対応しています。時には同じような質問に何度も回答したり、商品やサービスに対する苦情やネガティブな意見を聞いたりすることもあるでしょう。こうした業務負荷や精神的な負担が原因となり、離職につながってしまうケースも少なくありません。
しかしボイスボットを導入すれば、簡易的な問い合わせやよくある定型的な質問を無人対応で完結させることができます。またCRM(顧客管理システム)などと連携して、クレーマーからの電話をすべてボイスボットに対応させるといったフローを組むことも可能です。
これにより、オペレーターは重要な問い合わせや電話対応以外の業務に注力できるようになります。業務負担はもちろん、精神的な負荷も軽減できるでしょう。こういった取り組みを組織全体で実現できれば、人材の定着率も向上し、コールセンターの安定した運営が可能になります。
コールセンターにおける理不尽なクレーム(=カスタマーハラスメント)に対しては、ボイスボットなどのAI活用が効果的です。
人件費の削減につながる
コールセンターでは、コストの中でも人件費が大きなウェイトを占めます。ボイスボットの導入により、こうした人件費の削減が可能です。
たとえば、ボイスボットに搭載されているFAQ機能を利用すれば、定型的な問い合わせを「よくある質問」のページに案内できます。顧客の自己解決が可能となり、電話でのやり取りが減る分、より少ない人数のオペレーターで業務を回せるようになります。
ボイスボットを導入すれば、繁忙期や早期離職に備えて大量のオペレーターを雇用するといった対応も必要なくなります。
顧客満足度向上・機会損失の回避につながる
ボイスボットは自動対応が可能です。そのためオペレーターが席を外している場合や、人員を確保しにくい夜間なども含め、24時間を通して顧客からの問い合わせに対応できるようになります。24時間365日稼働できるコールセンターを外注するには多くのコストを要しますが、ボイスボットであればコストを最小限に抑えられます。
これにより、顧客は「電話がなかなかつながらない(=あふれ呼)」や「受付時間になるまで相談できない」といった不安やストレス、もどかしさを抱かずに済みます。いつでも好きなタイミングで問い合わせができるため、顧客満足度の向上につながるでしょう。また企業にとっても、企業にとってもオペレーターの不在で電話に出られない、または受付時間外のため顧客がアクションを起こせない、といった機会損失を削減できるというメリットがあります。
関連記事はこちら
シナリオを変更しやすい
ボイスボットは顧客からの質問を想定してシナリオを作成する必要がありますが、このシナリオは、音声認識に使用する表現や言葉を変えるだけで容易に変更が可能です。シナリオ作成後も状況に応じてどんどん改善していけます。
事前のシナリオ設計が必要なのはIVRも同様です。しかしIVRの場合、回答制度を高めるために分岐を増やす必要があったり、そもそも柔軟な設定が難しかったりと、シナリオ変更時に手間や費用がかかる傾向にあります。しかしボイスボットであれば、こうした課題もありません。
ボイスボットが活用されているシーン

ボイスボットはさまざまな場面で活用されています。どのようなところで使われているのか、具体的な活用シーンを見ていきましょう。
通信販売の注文受付
電話で注文を受け付けるタイプの通信販売は、「購入する商品の番号」や「支払方法」など、定型的な質問をするだけで完結できる傾向にあります。こうした簡単な電話受付にボイスボットを活用することで、注文を素早く自動的に注文を処理できます。
テレビで商品を紹介した際など、一時的に注文件数が多くなる場合でも、ボイスボットであれば応答率の向上が実現可能です。
ホテルや飲食店の予約受付
飲食店や宿泊施設の代表電話番号には、予約もしくはサービス内容に対する問い合わせの電話が多くかかってくる傾向にあります。しかしコールセンターのように電話業務に特化しているわけではないため、電話対応を専属で行う従業員がいないケースも珍しくありません。その場合、手の空いている従業員がメイン業務の合間を縫って対応することとなるため、業務負担が増加しがちです。
このようなケースでもボイスボットが活用できます。予約や問い合わせを自動的に処理できるため、業務効率化が可能です。また多言語対応のボイスボットを導入することで、外国語での予約受付もスムーズに対応できるようになります。
官公庁や地方自治体の電話受付
ボイスボットは、官公庁や地方自治体などの電話受付でも活用されています。
公的機関には、日頃から地域住民から多くの電話が寄せられます。地域のイベントや一時的な補助金の支給などがある際は、問い合わせが集中するケースもあるでしょう。しかしボイスボットであれば、入電数が多い場合でもスムーズに対応可能です。利用者を適切な窓口へ誘導したり、よくある質問の回答を提示したりする業務でも、ボイスボットが自動対応してくれます。
ボイスボットを導入する際の注意点

ボイスボットを導入する際は、複雑な内容の問い合わせに対応しにくい点や、正しく情報が伝わらない可能性がある点など、気をつけることがいくつかあります。
ここからは、導入時の注意点について詳しく見ていきましょう。
複雑な内容の問い合わせに対応しにくい
ボイスボットを導入する場合、音声以外を認識できない、あるいは複雑な文章構造の発話は解読できない点に注意が必要です。
IVRの場合は、顧客がプッシュボタン操作を間違えない限り、問い合わせ内容に即した担当者や担当部署に接続されます。しかしボイスボットは顧客の発話内容から問い合わせ内容を判断するため、発音の仕方が悪かったり、雑音が混じっていたりすると正確に聞き取れず、AIが適切に判断できないことがあります。
また、シナリオに用意されていないパターンで顧客が質問した場合も、AIが問い合わせ内容を読み取れない可能性が生じます。
このような課題に対処するには、聞き取れなかった内容や不適切な回答事例を検証し、シナリオのパターンを追加・修正することが大切です。繰り返しその作業を行うことで、ボイスボットの認識精度が高まります。
正しく情報が伝わらない可能性がある
ボイスボットは、テキスト化した情報の解読や読み上げに長けているので、単純かつ定型的なやり取りが得意です。
しかし人間同士のやり取りでは、テキストに加え、テキスト以外の情報も同時に扱って物事を伝達します。そのため画像や動画など、可視化できる情報がなければ理解しにくい内容を伝えるシーンでは、ボイスボットのみだと充分に機能しないことも考えられます。
電話の場合、画像や動画などは使わず、音声のみで相手に意図を伝えなければなりません。このようなコミュニケーション環境でボイスボットを活用すると、正しく情報が伝わらない可能性があるため、問い合わせ内容の難易度が高い場合は有人対応に切り替える対策を取るとよいでしょう。
ボイスボットを選ぶポイント

ボイスボットを選ぶ際に押さえておきたいポイントについて、それぞれ詳しく解説します。
有人対応への切り替えの有無
前述のとおり、ボイスボットはすべての問い合わせに対応できるわけではありません。問い合わせ内容によっては有人対応が必要になる場合もあります。有人対応への切り替えの有無やスムーズに切り替えられるかどうかなど、入念に検討しましょう。
特に、顧客が商品やサービスに対する苦情やネガティブな意見等を抱えて架電してきた場合、ボイスボットによる対応を続けることで不満を高めてしまう恐れがあります。その場合、AIが顧客のネガティブな感情を察知して即座に有人対応へ切り替えられる機能があれば、不満が高まる前に適切に対応できます。このようにして、顧客満足度の維持や向上を目指しましょう。
関連記事はこちら
内容確認機能の有無
ボイスボットの内容確認機能とは、電話で受付完了した内容をテキスト化し、通話後にメールやSMSなどで顧客に送信する機能のことです。これにより、顧客が電話で行った手続きに関して、後から内容を確認できます。
前述のとおり、ボイスボットの音声認識精度は絶対のものではありません。場合によっては顧客の声を正確に聞き取れず、適切な判断ができないこともあります。そのため受け付けた情報に誤りがないかどうかを顧客が確認できるよう、フォローアップ機能がある製品を選ぶのがおすすめです。
自動学習機能の有無
自動学習機能があるボイスボットの場合、AIが自ら学習を行うため、効率よく回答精度を向上できます。
一方、自動学習機能がないボイスボットには、手動でのチューニングが必要です。管理者が直接会話データを分析・管理するため、自動学習機能があるものに比べて管理工数が増えやすい傾向にあります。チューニングの工数を抑えるなら、自動学習機能があるボイスボットを選ぶのがおすすめです。
ただし、AIが自ら学習する場合、誤ったデータを取り込んでしまうリスクも考えられます。このようなメリット・デメリットを理解したうえで、自社にとって最適なタイプを選びましょう。
他システムとの連携範囲
ボイスボットの多くは、業務で利用している既存システムと連携できるものもあります。連携可能なシステムとして挙げられるのは、以下のとおりです。
- CRM(顧客管理システム)
- RPA(ロボティックプロセーション)
- ビジネスチャットツール
など
ボイスボットと連携するシステムが増えるほど、機能が拡張され、対応できる範囲が広がります。製品によって連携範囲が異なるため、検討時には注意しましょう。
音声サンプルの種類
コールセンターなどの電話対応では、音声次第で相手が受ける印象が大きく変わります。そのため、ボイスボットを選ぶうえで「どのような音声サンプルを選べるか」や「種類はどの程度あるか」といった点は重要です。
ボイスボットの音声サンプルには、次のような種類があります。
- 男性の声・女性の声
- 明るい声・穏やかな声
- 落ち着きのある声
など
製品によっては、声の調子まで細かく設定できるものもあります。自社のブランドイメージや顧客の属性などに合わせて、どのような音声が最適か検討しましょう。
ボイスボットを活用するためのポイント

ボイスボットを活用するためのポイントについて詳しく見ていきましょう。
定期的にチューニングを行う
ボイスボットの回答は常に完璧なわけではありません。時には誤認識や誤回答をしてしまう可能性があります。これらを防ぐには、自動学習機能の有無に関わらず、定期的にシステムをチューニングして精度を高めることが大切です。あらかじめ認識ミスが発生しやすい箇所を特定したうえで、会話の流れやシナリオなどを見直すとよいでしょう。
取得した音声データを施策改善に活かす
ボイスボットの中には、電話の会話内容を自動的に保存できる製品があります。音声データを取得・テキスト化することで問い合わせ内容を分析できるため、その結果を施策の改善に活かせるのがメリットです。また音声データの蓄積によって、顧客のニーズを把握したり、ボイスボットの回答の精度を高めたりといったこともできます。
まとめ
ボイスボットは、AIを活用することで顧客対応の効率化やオペレーターの負担軽減、人件費の削減、顧客満足度の向上、機会損失の回避などを実現するシステムです。
一方で、複雑な内容の問い合わせに対応しにくいことや、正しく情報が伝わらない可能性があるなど、いくつかの注意点もあります。ボイスボットを導入する際は、これらの注意点を踏まえたうえで、自社の業務内容に合致するシステムを選びましょう。
執筆・監修者
- カテゴリ:
- コンタクトセンター