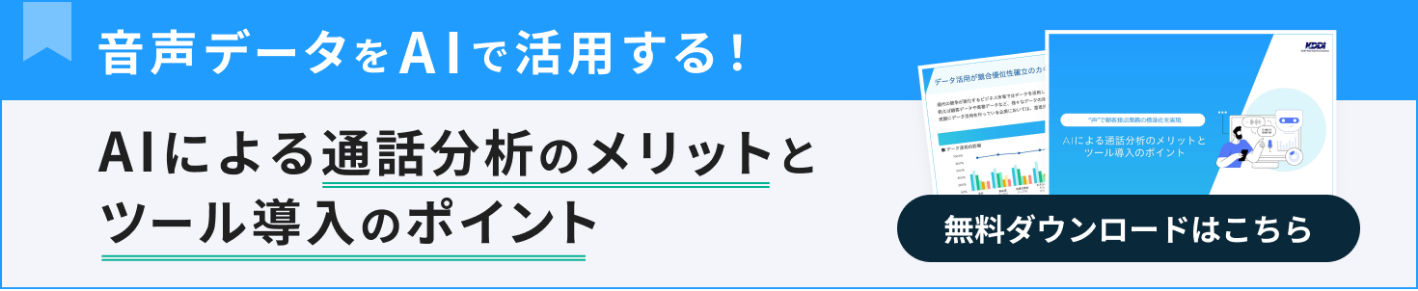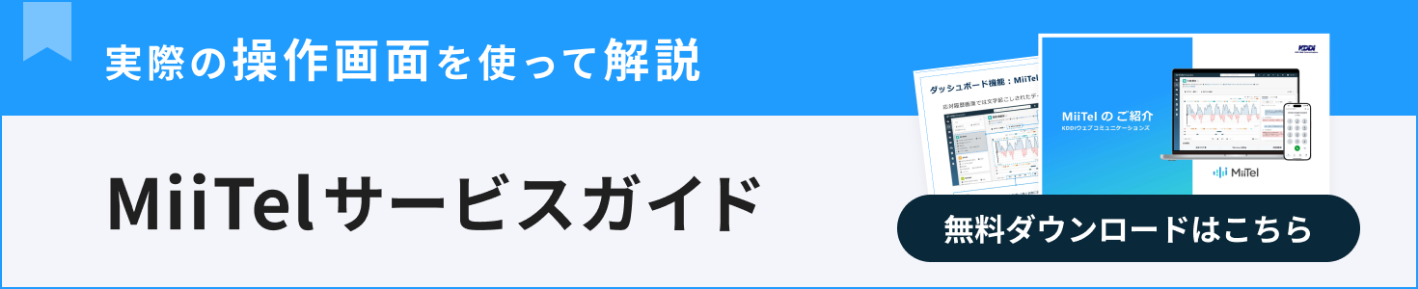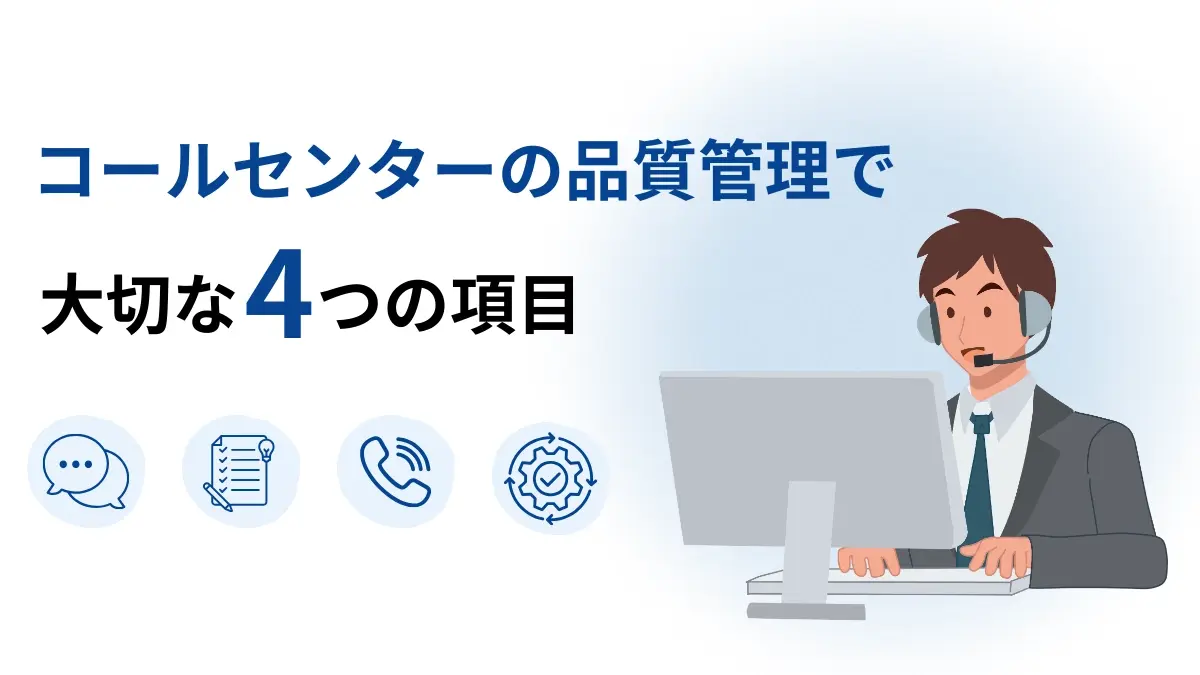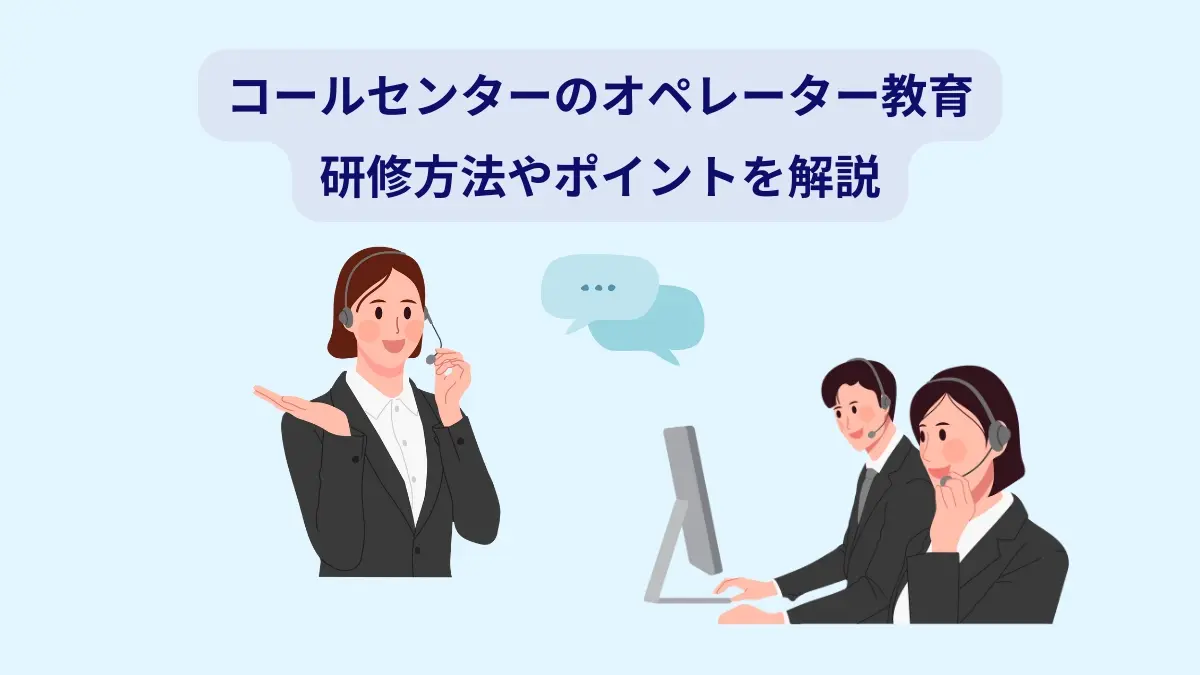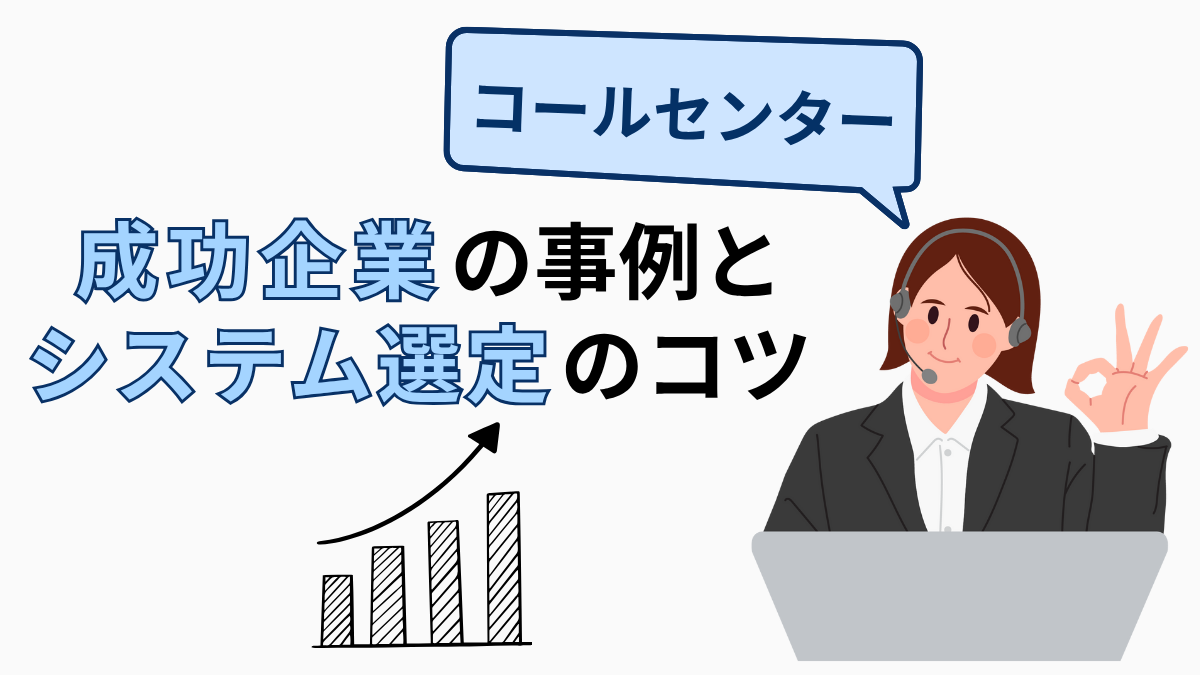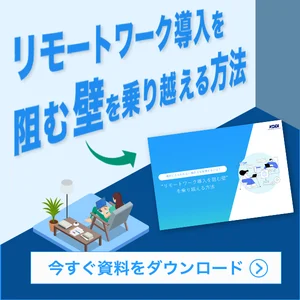クラウドコールセンターとは?主な機能や導入するメリット・デメリット、選び方を解説
更新日:
公開日:
KDDIウェブコミュニケーションズ

高機能なシステムやソフトウェアをクラウド上で利用できるサービスが増加している昨今。コールセンター業界においてもテレワークの推進・普及を背景に、コールセンターシステムのクラウド化が少しずつ進んできています。
クラウドコールセンターシステムには初期費用や運用コストを抑えつつ業務効率化や顧客満足度向上を実現できる、というコールセンター運営上のメリットがある一方、データ管理のリスクなどに不安を覚える方もいるのではないでしょうか。
本記事ではクラウドコールセンターの基本的な仕組みや機能を解説するとともに、導入のメリット・デメリット、システム選定の際の重要ポイントを詳しく紹介します。
社内の課題解決や、コールセンター業務のさらなる発展のヒントを見つけるためにも、クラウドコールセンターの導入を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
クラウドコールセンターとは

クラウドコールセンターとは、コールセンターを運用するのに必要な機能やシステムをオンライン上で利用できるプラットフォーム、またはそのプラットフォームで運営されるコールセンターのことを言います。特に前者は「クラウドコールセンターシステム」とも呼ばれています。
基本的にログインIDやパスワードを使ってログインし、Webブラウザ上で利用する仕組みになっています。そのためソフトウェアのインストールが不要で、導入コストや運用コストを抑えられるほか、専門的な知識がなくても運用しやすいというメリットがあります。
またコールセンターシステムには「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類がありますが、クラウド型の場合はインターネット環境があれば場所を問わずに利用できるのもポイントです。オンプレミス型の場合は自社でサーバーやネットワークなどのハードウェアを構築してからシステムを稼働させなければならないため、大きな違いがあると言えるでしょう。
クラウドコールセンターシステムの主な機能

クラウドコールセンターシステムには、業務効率や顧客対応の質を高めるための便利な機能がたくさん用意されています。ここでは、主要な機能をピックアップしてみていきましょう。
CRM連携
CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客情報や問い合わせ履歴などを一元管理するためのシステムです。顧客の属性や過去の問い合わせ内容、あるいは営業やマーケティング部門とデータを連動させられます。そのため店舗での購入履歴やWebサイトのアクセス履歴、会員情報のようなデータ管理も可能です。
またCRMをCTI連携すれば、画面上に表示された顧客情報を見ながらリアルタイムで問い合わせ対応を行えます。迅速に顧客情報を照会でき、過去の問い合わせ内容をもとに対応を最適化できる仕組みです。結果として応対品質が高まり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
IVR
IVR(Interactive Voice Response)とは、音声自動応答システムのことです。たとえば「商品に関するお問い合わせは1番を、価格に関するお問い合わせは2番を」といった形で機械による案内を設定できます。顧客がプッシュボタン操作を行うことで、問い合わせ内容に応じたオペレーターや担当部署に着信が振り分けられる仕組みです。IVRを使えば1次対応を自動化できるため、業務効率化につながります。問い合わせ内容次第では、営業時間外に対応できる点もメリットです。
関連記事はこちら
ACD
ACD(Automatic Call Distribution)とは、事前に設定したルールにしたがって、着信した電話を適切なオペレーターに振り分ける機能です。システム上にオペレーターの稼働状況(空き状況)やスキルのような条件を設定し、その条件を問い合わせ内容に照らし合わせて、自動的に最適なオペレーターや担当部署に振り分けることが可能です。
関連記事はこちら
IP電話(ブラウザフォン)&スマホアプリ
IP電話(ブラウザフォン)とは、インターネット回線を利用して通話できる機能のことを指します。一般的な固定電話のように電話網を通じて音声を伝送するのではなく、データ化した音声をインターネット上でやり取りすることにより、ブラウザ上での通話が可能になります。またIP電話の中には、スマートフォンのアプリと連携可能なものもあります。
クラウドコールセンターシステムがあれば、ブラウザやスマホアプリを通じて、いつでもどこでもコールセンター業務ができます。特別なソフトをインストールする必要もありません。
通話録音
顧客との通話内容を録音できる機能です。これにより顧客とのやり取りを後からでも確認でき、聞き逃しや聞き間違いを防げます。言った・言わないを原因としたトラブルやクレームの防止策として活用すれば、オペレーターの精神的負担の軽減につながるでしょう。
さらにオペレーター自身の対応の振り返りや、各オペレーターの対応分析・マニュアル化にも役立てられます。効率的なオペレーター教育にも寄与する機能です。
自動文字起こし・自動要約
自動文字起こし機能とはその名のとおり、通話内容を自動でテキスト化する機能のことを指します。先に挙げた通話録音機能が聴覚的に通話内容を記録する手法なのに対し、自動文字起こし機能では通話内容を視覚的に記録します。
問い合わせ内容の対応漏れを防げるほか、対応履歴をテキストデータとして蓄積しやすいのが特徴です。VOC(顧客の声)の収集、オペレーターの応対品質の改善にも活用しやすくなります。
中には自動で文字起こしをするだけでなく、その内容をAIによって自動要約する機能が搭載されているものもあります。問い合わせ内容を端的に把握しやすくなることで、さらなるオペレーター業務の効率化および品質向上に貢献するでしょう。
トーク分析・感情分析
トーク分析とは、オペレーターと顧客の通話内容を解析して「会話の流れが自然であるか」や「わかりやすく提案内容を伝えられているか」を評価する機能です。オペレーターの稼働率や応答時間、顧客対応の録音データやテキストデータなど、クラウドコールセンターシステム内に蓄積されたデータをもとに分析・評価を行います。
また、感情分析機能とは、オペレーター・顧客の音声の周波数をAIが解析できる機能です。楽しさや怒り、悲しみ、満足感などの感情をAIが読み取ります。これらの分析結果を振り返ることでオペレーターの教育に活用でき、成約率の向上や顧客満足度の維持・向上につなげられます。
コールキューイング
コールキューイングとは、電話回線よりも入電が上回った場合に、電話がつながらないままの着信を一時的に留めておく機能のことです。電話がつながるのを待っている顧客の状態を「あふれ呼」や「待ち呼」といいます。
あふれ呼状態の顧客に対して「ただいま大変混み合っております。もうしばらくお待ちください」などのガイダンスを流します。クラウドコールセンターシステムによってはAIの活用により待ち時間を伝えてくれるものもあるため、「なぜかわからないが電話がつながらない」、「いつまで待てばいいかわからない」といった状態を防ぎ、顧客のストレスを軽減します。
また回線が空き次第、順次対応するための着信順序の管理も可能です。
関連記事はこちら
ウィスパリング
ウィスパリングとは、オペレーターと顧客のやり取りを上長やSVが遠隔で聞きながら、対応に関する指示やアドバイスを出せる機能です。リアルタイムで指示・アドバイスを出せるため、トラブルやクレームの発生防止が期待できます。
経験の浅い新人オペレーターに対して適宜サポートを提供できるため、社内研修としても役立てられます。この機能を利用してコーチングなどを行えれば、新人オペレーターも安心して業務に臨みやすくなるでしょう。
関連記事はこちら
プレディクティブコール
プレディクティブコールとは、あらかじめ設定した特定のリストの連絡先に対し、自動で一斉発信する機能です。同時発信してつながった電話のみを自動的にオペレーターに接続するため、リストの情報を追いながら1件ずつ架電する手間がかかりません。電話がつながるまで待機する時間も省けるため、コールセンター業務の大幅な工数削減に貢献します。
クラウドコールセンターのメリット

コールセンターをクラウド化することにどのようなメリットが得られるのか、代表的なメリットを5つ紹介します。
初期費用や運用コストを抑えやすい
クラウドコールセンターは、オンプレミス型のコールセンターと比べて初期費用を抑えやすい傾向にあります。クラウドコールセンターシステムはパソコンとインターネット環境があれば導入可能なため、インフラ構築費やソフトウェアのライセンス料といった初期費用がほとんど必要ありません。またインフラ周りの定期メンテナンスやライセンス更新が不要といった魅力もあります。
ほかにも、料金体系の多くが従量課金制であるという点もメリットとして挙げられます。利用量に応じて料金が設定されるため、月額利用料のような運用コストもコールセンターの規模に応じて最適化が可能です。
オペレーター・管理担当者の業務負担や不安を軽減できる
オンプレミス型のコールセンターシステムの場合、インフラ構築やシステム開発、データ移行などが必要で、導入までに数ヶ月程度の期間を要するケースもあります。導入後も保守・運用対応が欠かせないため、オペレーターや管理担当者の負担が増えやすいです。
一方クラウドコールセンターシステムは、Webブラウザ上でシステムにログインするだけで利用開始できます。ログインIDやパスワードも即時発行可能です。インフラ構築やシステム設計などの必要がない分、迅速なサービススタートを実現します。また導入後のメンテナンスやアップデートもベンダー側が対応するため、オペレーター・管理担当者の業務負担を削減できます。オペレーターや管理担当者は顧客対応などのより重要な業務に集中でき、結果としてコールセンターのさらなる品質向上にもつながるでしょう。
またクラウドコールセンターでは、実際に顧客対応を行うオペレーターを支援する機能が充実しています。たとえば感情分析やトーク分析によって最適な応対ができるよう詳細なマニュアルを作成したり、ウィスパリングによって応対中にもリアルタイムでオペレーターに指示を出したりできます。これによりリモート環境であっても、経験の浅いオペレーターも安心して業務に当たることができるのです。
柔軟な働き方に対応しやすい
クラウドコールセンターでは、インターネット環境があれば場所を問わずにシステムにアクセスできます。テレワーク中に従業員個人のパソコンを利用する場合でも、インターネットにつながっている状況でログインIDとパスワードを入力すれば、Webブラウザからシステムにログインが可能です。
これに対してオンプレミス型のコールセンターでは、社内やデータセンターにサーバーやネットワーク、システム基盤などの設置が求められます。運用するために物理的な拠点が必要な分、働き場所が制約されがちです。
クラウドコールセンターであれば働く場所の制約を受けないため、テレワークや在宅コールセンターなどの柔軟な働き方に対応しやすいと言えます。
関連記事はこちら
顧客満足度の向上が期待できる
クラウドコールセンターシステムには、AIを活用したさまざまな機能が搭載されています。
たとえばCRM連携によって顧客情報を対応中もリアルタイムで確認できるため、顧客ごとにパーソナライズ化した適切なオペレーションを提供できます。またウィスパリング機能によってオペレーターの教育を行いながら最適な提案・対応を行うことも可能です。
対応後も自動文字起こし・自動要約機能で情報を整理しやすくなるほか、応対の録音データなどから感情分析を行うことで、顧客対応をブラッシュアップしていけます。こうした分析や改善により、顧客満足度の向上につながるでしょう。また各機能の活用によりオペレーターの業務効率も向上するため、顧客1人当たりの応対時間を短縮することも可能です。これにより待ち呼・あふれ呼の発生を防ぎ、顧客ストレスを軽減できます。
さらにクラウドコールセンターシステムの場合、電話に加えてアプリやSNSなど、新たな問い合わせチャネルとの連携および拡張も簡単です。電話以外での問い合わせを望む顧客のニーズにも対応しやすくなるでしょう。
関連記事はこちら
スケーリング調整をしやすい
クラウドコールセンターシステムは、オンプレミス型のようにスケールに応じてインフラ構築、システム設計をする必要がありません。多くのサービスは、複数用意されている月額制のプランを選択するだけです。
スケーリング調整の際は、プラン変更とオプションの増減だけで済みます。繁忙期や急な人員増加などにも迅速に対応できるほか、必要な分だけリソースを増やすことで、コールセンター運営における無駄なコストを抑えられます。
クラウドコールセンターのデメリット

クラウドコールセンターにはメリットが多い一方で、いくつか注意しなければならない点もあります。どのようなデメリットがあるのか見ていきましょう。
独自のカスタマイズが難しい
クラウドコールセンターシステムは、ベンダーがハードウェアやシステムを管理しています。そのため、個別の要件に合わせてカスタマイズするのが困難です。自社の業務プロセスや要件に沿ってシステムを調整しにくく、コールセンターの運営が制限される可能性もあります。
システムに標準搭載されていないワークフローや分析機能を追加したい場合、それらの要求に100%対応するのは難しいでしょう。規定品にはない独自の機能を持たせることや、厳格なセキュリティ対策をシステムに反映させる場合は、システムを柔軟に設計できるオンプレミス型のコールセンターシステムの方が向いています。
セキュリティリスクが高まる可能性がある
顧客情報を扱うコールセンターには、強固なセキュリティ対策が欠かせません。しかしデータがクラウド上に蓄積されるクラウドコールセンターシステムでは、クラウド上のデータが常にインターネットと接続されています。
そのため、サイバー攻撃や不正アクセスによる情報漏えいのリスクが付きものです。それらによる損害賠償請求などの大きなトラブルも発生するかもしれません。クラウドコールセンターシステムを選ぶ際は、データセンターのセキュリティレベルや実績など、ベンダーの信頼性をしっかりとチェックすることが大切です。
またサービスを利用する企業側は、多要素認証やユーザー管理、ログ監視など、社内で実施できるセキュリティ対策も忘れないようにしましょう。
クラウドコールセンターシステムの選び方

クラウドコールセンターシステムを導入する際は、自社の業務形態や規模に合わせた適切なシステム選びが必要です。ここでは、システムを選ぶ際の3つのポイントを解説します。
業務形態との相性
クラウドコールセンターシステムには、インバウンド向けとアウトバウンド向け、あるいはその両方に対応した製品があります。自社の業務形態によって向き・不向きが異なるため、慎重に判断しましょう。
顧客からの入電に対応するインバウンドでは、商品・サービスの注文受付や修理のサポート依頼、クレーム対応などがメイン業務となります。インバウンド業務を効率的に行うには、自動応答システム(IVR)やコールキューイングといった機能を搭載したシステムがおすすめです。さらなる生産性・顧客満足度向上につなげるのであれば、AI機能の搭載有無や他チャネルへの拡張性、および連携有無を確認するのが望ましいでしょう。
一方のアウトバウンドは、コールセンターから顧客へ架電を行う業務を指します。具体的には、アポイントメントの獲得や市場調査などがメイン業務です。アウトバウンド業務には、プレディクティブダイヤリングなど、電話発信を効率良く行える機能を備えたシステムを選んでください。
回線数・対応オペレーター数
クラウドコールセンターシステムは、製品によって回線数や対応オペレーター数が異なります。そのため自社の規模や運用計画に則って、適切な回線数・対応オペレーター数の製品を選ぶことが重要です。
また、将来的なコールセンターの拡張や縮小を事前に検討しておくことも大切です。事業の成長や変化に伴い、コールセンターの規模も変動する可能性があります。そのような状況に備えて、柔軟にスケーリングを調整できるコールセンターシステムを選びましょう。
セキュリティ
前述のとおり、クラウドコールセンターシステムにはインターネット環境に接続されたデータが攻撃の標的になる危険性や、情報を窃取されるリスクがあります。したがって、セキュリティ面が十分に保護された製品を選ぶのが原則です。
セキュリティを評価するには、セキュリティに関する実績や評判を調査する方法が挙げられます。データの保護や暗号化の手段、バックアップ・復旧方法なども、あわせて確認しておきましょう。
セキュリティ機能が充実しているほか、複数のセキュリティ認証資格を取得しているベンダーは安全性が高いと言えます。
まとめ
クラウドコールセンターは導入コストや運用コストを抑えつつ、業務の効率化や顧客満足度の向上が期待できるシステムです。導入によってスタッフの育成にもつなげられます。
しかし、独自のカスタマイズが難しい点や、セキュリティリスクがある点はデメリットでしょう。クラウドコールセンターの導入を検討する際は、自社の業務形態や規模に合わせて適切なシステムを選ばなければなりません。
クラウドコールセンターシステムの導入をお考えの方は、ぜひ「UJET」をご検討ください。UJETは、高度な機能と充実したサポートを兼ね備えたシステムです。初期費用なしで導入でき、柔軟にスケーリングできます。
UJETを利用して、コールセンター運営の効率化とコスト削減を実現しましょう。
執筆・監修者
- カテゴリ:
- コールセンター